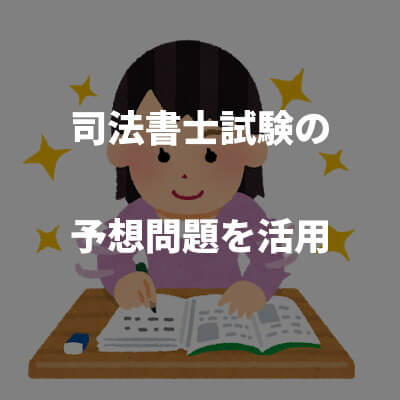おつかれさまです!資格ワン運営の司法書士「よしと」です。

予想問題をやっとけば試験に合格できないかな?
今年の司法書士試験の予想問題ってどれを選べば良いの?
そんな疑問はないでしょうか?
この記事では、司法書士試験の予想問題の特徴・種類と、予想問題にかかる費用や勉強効率など、以下の部分について説明していきます。
|
予想問題の勉強はあとひと押しに最適ですから、合格点までのあと数点のために上手に利用しましょう。
私自身は4年目の司法書士試験で合格しました。
最初の数年は予想問題に手をつけるまで勉強することができませんでしたが、予想問題を活用できた4年目に合格することができました。
その経験から、予想問題の種類だけでなく、使い方やおすすめ度までまとめていきます。
司法書士試験の予想問題は解くべき?
今年の合格を目指している人は、司法書士試験の予想問題を解いておくのがおすすめです。
なぜなら、本試験までに注力すべき分野が分かるなど様々なメリットがあるからです。
一方で、次のような人はまだ予想問題には手を付けなくても構いません。
- 勉強を始めてまだ間もない人
- 今年はお試し受験の人
- 今年の試験には明らかに間に合わない状況の人
これらの人は、予想問題を解くよりも講義・テキスト・復習・過去問演習といった基本的な勉強を頑張ったほうが、来年の合格に近づくことができるからです。
司法書士試験の予想問題を解くメリット
予想問題を解くメリットには以下のようなものがあります。
|
これらのメリットについて1つずつ説明していきます。
現時点での自分の実力が分かる
予想問題を解いてみることで、本試験でどのくらいの点数が取れるのかの目安にすることができます。
- 本試験で基準点を超えられそうなのか
- どのくらい上乗せ点を稼げそうなのか
といった予想ができるようになるため、今から本試験までにどのくらい勉強をしなければいけないか、勉強計画を立てることができます。
思った以上に得点できず、今年の合格は厳しそうだと感じた人も、来年に向けての長期的な勉強プランに早期に切り替えができ、来年の試験を有利に戦えるようになります。
苦手・弱点を把握できる
司法書士試験の予想問題を解くことで、過去問を解くだけでは把握しにくい、自分の苦手や弱点が分かり、効率的に対策することができます。
直前期の勉強時間は貴重なため、なるべく点数につながる勉強をしたいもの。
予想問題であなたが間違えてしまった苦手・弱点は、本試験で点数を稼ぐために最優先で対策すべき内容です。
このように予想問題を解くことで、直前期勉強の優先順位が明確になります。
本試験までに注力すべき分野が分かる
予想問題の正解・不正解に関わらず、予想問題で出題された分野は優先的に勉強しておきましょう。
なぜなら、予想問題は過去の出題をもとに、今年の出題確率が高い分野を集めて作られているからです。
直前期は試験範囲全体の復習をしますが、その中でも特に出題確率が高い分野を重点的に勉強したほうが、本試験で得点できる可能性が高まります。
そのため、予想問題に正解できたことで満足するのではなく、同じ分野には他にどんな論点があるかといったところまで勉強範囲を広げて復習すると良いでしょう。
司法書士試験の予想問題の注意点
予想問題を解くうえでは、以下のような注意点もあります。
|
これらの注意点について1つずつ説明していきます。
本試験との難易度の違い
予想問題は本試験よりも、少し難易度が高めのことが多いです。
なぜなら、易しめの問題を出してしまうと「問題が簡単すぎて役に立たなかった」というクレームが出てしまうからです。
予想問題は基本的に予備校が作っていますから、受験生に合格してもらうために少し難しめの問題を作っています。
そのため、予想問題が解けなくても、予想問題レベルまで解けるようになれば合格できるとポジティブに考えるようにしましょう。
全く同じ問題が出るわけではない
予想「問題」という名称ではありますが、予想されているのは出題「分野」までであり、本試験で全く同じ問題が出るわけではありません。
予備校は、過去の出題実績から今年の出題分野を予想しています。
どれだけ過去の傾向を分析しても、ドンピシャで出題される条文や判例を予想できるわけではありません。
そのため、予想問題はその問題自体が解けることよりも、問題の周辺知識もどのくらい理解できているか、正解できるかといったように考えてください。
予想問題を解けば点数が上がるわけではない
予想問題はあくまで本試験までの勉強に役立てるものであり、予想問題自体を解いても点数は上がりません。
また、色々な予想問題をとにかく解きまくることにもあまり意味はありません。
予想問題を解くことは、直前期の勉強方針や勉強内容を決めるのに役立ちます。
しかし、何種類も予想問題を受けると勉強範囲がどんどん広がってしまい、結局は試験範囲全体を勉強するのとあまり変わらなくなってしまいます。
色々なパターンで自分の実力をチェックしたいのであれば、複数の予想問題を解くのも良いですが、これからの勉強を効率化したいのであれば、予想問題は適度に絞り込みましょう。
司法書士試験の予想問題4種類
予想問題と言っても本試験と同じような問題から、予想論点のまとめまで様々な形式があります。
それぞれ向き不向きがありますので以下の予想問題の特徴を説明をしていきます。
|
予想問題1:予想問題集
毎年、早稲田経営出版から司法書士試験の「本試験予想論点表」と「本試験予想問題集」が発売されています。
大手予備校Wセミナーの講師陣の出題予想から作られているので予想論点、予想問題としては信頼のおけるものになっています。
5段階で評価するなら以下のとおり。
| 予想論点の学習 | 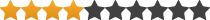 (4 / 10) (4 / 10) |
| 予想問題 | 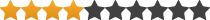 (4 / 10) (4 / 10) |
| その他の活用 | 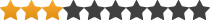 (3 / 10) (3 / 10) |
| 価格 |  (5 / 10) (5 / 10) |
| おすすめ度 |  (5 / 10) (5 / 10) |
予想論点と予想問題をそれぞれ一冊にまとめているので情報の網羅性が高く、予想論点や予想問題の学習としてのほか、直前期の重要論点チェック用のテキストとして利用することもできます。
なにより、他の予想問題と比べて格安なのが強みです。
書籍での予想論点、予想問題の勉強は一通り試験範囲を学習済みで自分で直前期の勉強スケジュールを立てられる人におすすめ。
なぜなら、自分で主体的に勉強ができないと「本は買ったけど結局開かなかった」なんてことになる可能性が高いからです。

手が空いたらやろう。
と思っているのであれば、他の方法の方が良いでしょう。
予想論点、予想問題の書籍はTAC出版公式サイトからであれば10%~15%割引で購入可能です。
LECも同じように予想問題集を販売していますので、こちらを利用するのもアリです。
スポンサーリンク
予想問題2:答練
各予備校の答練もその年の予想問題の側面があります。
特に各社の1番最後の時期に実施される答練は総合的な出題で、司法書士試験の予想問題も兼ねています。
5段階で評価するなら以下のとおり。
| 予想論点の学習 | 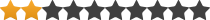 (2 / 10) (2 / 10) |
| 予想問題 | 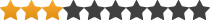 (3 / 10) (3 / 10) |
| その他の活用 | 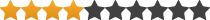 (4 / 10) (4 / 10) |
| 価格 | 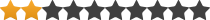 (2 / 10) (2 / 10) |
| おすすめ度 | 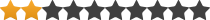 (2 / 10) (2 / 10) |
予想問題の本命は答練よりも模試で出題されることが多いので、答練は模試だけでは出題しきれなかった論点の補完の意味合いがあります。
また、論点解説の使い勝手は他のものに比べると落ちるので、予想論点、予想問題のためというよりは試験テクニックの練習や記述の練習、時間配分の調整、知識が身についているかの確認といった使い方をしたほうが効果的でしょう。
価格は少しお高めなのが難点です。
答練は司法書士試験の基準点を超えるくらい勉強が進んでいる人におすすめ。
なぜなら、試験形式での練習は新しい知識を覚えるよりも知識を上手に使って得点を伸ばすのに最適だからです。
そのため、予想問題としてのおすすめ度は低めに評価しています。
予想問題3:模試
司法書士試験の直前期に多数行われる模試はまさに予想問題と言えます。
難易度も比較的高めで本試験と同じかそれ以上に難しい出題がされることも多いです。
5段階で評価するなら以下のとおり。
| 予想論点の学習 | 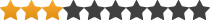 (3 / 10) (3 / 10) |
| 予想問題 |  (5 / 10) (5 / 10) |
| その他の活用 |  (5 / 10) (5 / 10) |
| 価格 | 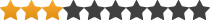 (3 / 10) (3 / 10) |
| おすすめ度 | 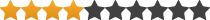 (4 / 10) (4 / 10) |
模試の問題は予想問題として精度が高いものが多いですが、やはり他の教材と比べると実践的な側面が強く、「模試で予想論点を勉強する」という使い方にはあまり適していません。
しかし、模試を受ける人は答練に比べても多いため、自分の順位をより正確に把握できたり、本試験での出題確率が高い問題で知識のチェックができたりと直前期の学習進行度を測るものさしとしては非常に有用です。
価格も答練に比べるとリーズナブルなので比較的受けやすいです。
模試は初学者でまだ一通り学習が終わっていないという人以外の幅広い人におすすめ。
なぜなら、今年の合格を目指すのに役立つのはもちろん、直前期に自分の弱点を把握しておけば来年以降の勉強指針にもなるからです。
予想問題の学習をするには活用がやや難しいので、予想問題としてのおすすめ度はそこそこです。
| 関連記事:「【2023年向け】司法書士試験おすすめ模試スケジュール・活用法まとめ」 |
予想問題4:直前期対策講座
直前期になると各予備校ではさまざまな対策講義を実施します。
その中には出題予想論点や予想問題について扱う講座もあります。
5段階で評価すると以下のとおりです。
| 予想論点の学習 |  (5 / 10) (5 / 10) |
| 予想問題 | 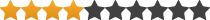 (4 / 10) (4 / 10) |
| その他の活用 | 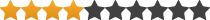 (4 / 10) (4 / 10) |
| 価格 | 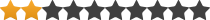 (2 / 10) (2 / 10) |
| おすすめ度 | 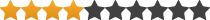 (4 / 10) (4 / 10) |
直前期対策講座は書籍で勉強するのに比べて講義が付いてくる分、予想論点の学習には最適です。
予想論点の中でも重要度が高い、低いという部分を講師の説明から感じることもできるので司法書士試験に一番役立つ予想論点対策と言うことができます。
論点の学習に重点が置かれていることが多いので、予想問題の演習としては模試に一歩劣る部分がありますが、予想論点をきちんと理解できた方が本試験に対応しやすいです。
直前期の重要論点の総復習としても使えるのであなたの得点を全体的に底上げしてくれる効果も期待することができます。
いたれりつくせりである分、価格はお高めなのが難点。
直前期対策講座は今年絶対に合格する!という人におすすめ。
なぜなら、価格は少し高いものの予想論点学習としては一番有用な学習方法だからです。
コスパで考えるなら書籍には少し劣るかと思いますので、予想問題としては結構おすすめくらいにとどめています。
司法書士の予想問題4種類の効果・おすすめ度【予想問題集・答練・模試・直前期講座】
司法書士試験の予想論点、予想問題は色々な方法で提供されています。
特に予想論点の学習に適しているのは
|
の2つです。
あなたが主体的に勉強スケジュールを立ててこなすことができるのであれば書籍。
定価1,760円 → 公式サイト1,584円(10%引き)
定価1,980円 → 公式サイト1,782円(10%引き)
定価3,740円 → 公式サイト3,179円(15%引き)
最適な時期に教えてもらいたい、詳しく説明して欲しいのであれば直前期対策講座を利用した方が良いでしょう。
予想問題の演習に適しているのはなんといっても模試です。
模試は幅広い人が活用できるので、初学者で一通り範囲を終えるのに苦労している状態でなければ受けておくのがおすすめです。
直前期に予想論点、予想問題の勉強をしておくことで本試験で1問以上多く得点できるようになることはよくあります。
あと1問が合否を分ける司法書士試験ですから上手に活用して合格者に入れるようにしましょう!