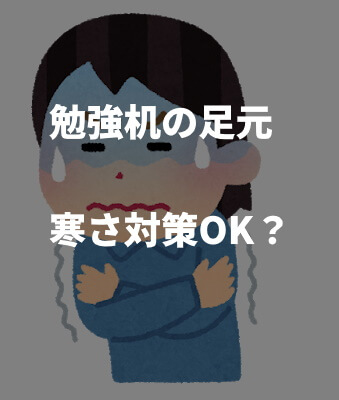おつかれさまです!資格ワン運営の司法書士「よしと」です。
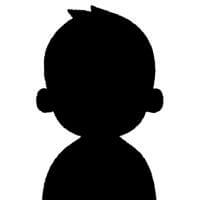
冬は机で勉強していると足元が寒い!足元を温める良い方法はない?
そんな風に思っていないでしょうか?
この記事では、冬場に足元を温めながら勉強することの必要性と、様々な寒さ対策について説明します。
対策の特徴に触れて、主に良くなかった、困った点について解説していきます。
毎年冬になるたびに足元の寒さ対策を色々試しているうちに、無事に司法書士試験に合格した私の使用経験に基づいてお話します。
冬場の勉強机・デスクの足元寒さ対策が必要な理由
勉強と室温は関係が深く、少し涼しいと感じるくらいが勉強の最適な室温です。
具体的には
| 季節 | 最適な室温 |
| 夏 | 25度くらい |
| 冬 | 18度くらい |
が適切。
寒い冬は上半身ははんてんなどを羽織れば簡単に防寒できますが、長時間勉強を続けていると足元が冷えてきます。
足元が寒いのをちょっと我慢して勉強していると気付かないうちに体温が下がって免疫力が下がり、風邪やインフルエンザにかかりやすくなってしまいます。
しかし、エアコンの温度設定を上げると部屋の上部から温まりやすいため、勉強中にぼーっとしてしまったり、眠くなる原因になります。
そのため、冬場はきちんと足元用の対策をしておくほうがベターです。
冬の足元の寒さ対策7つを比較
足元の寒さ対策グッズは色々とありますが、それぞれに特徴があります。
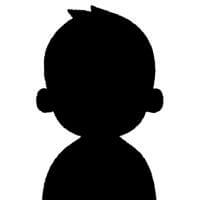
実際に使ってみたけど一部しか温まらず、まだ寒かった
なんてことにならないよう、私が実際に使った感想も交えて比較していきます。
温まる部位については、
|
の3ヶ所に分けて比較します。
温かさは5段階評価で、数字が大きほど温かいという表示です。
足元寒さ対策1:遠赤外線セラミックヒーター
| 価格 | 74,800円~ |
| 電気代(1時間あたり) | 13円~ |
| 足 | 4 |
| すね | 5 |
| ふともも | 5 |
| 動きやすさ | 5 |
遠赤外線セラミックヒーターは空気を温めるのではなく、ヒーターの両面から遠赤外線を照射して温めるため、ヒーターの近くはすぐ暖かく、部屋全体も暖かくなります。
温風を出すヒーターではないので運転音が静かで、勉強や作業に集中しやすいのもメリット。
部屋が乾燥せず、机に向かって集中していても喉が痛くなってきたりすることがありません。
電気代は1時間あたり13円~と、他の足元寒さ対策よりは電気代は高めなので、足元が暖かい以外の要素にも価値を感じられる人でなければ、他の方法を選んだほうが良いかもしれません。
肝心の足元ですが、ヒーターパネルの面積が大きいので、足、すね、ふとももと広範囲で暖かく、あまり近くで当たっていると熱くなってくるくらいには足元の暖房効果は高めです。
パネルの表面全面にメッシュ状のカバーがされているため、勉強中に足や手が触れてしまっても火傷するような熱さではないです。
他の暖房器具と比べると高額ですが、勉強している時の動きを一切邪魔せず、足元も足元以外も暖房効果が高いので、快適さを重視するならアリ。
スイッチをつけてすぐ暖かく、足元も部屋全体もかなり暖まる。
運転音がほとんどしないので勉強に集中しやすい。
温風ではないので部屋が乾燥せず、喉が痛くなってりしないのも嬉しい。
突然の来客時にもパッと席を立て、動きが制限されないので、勉強していても煩わしさがありません。
足元寒さ対策2:カーボンヒーター
| 価格 | 4,000円~ |
| 電気代(1時間あたり) | 8円~ |
| 足 | 3 |
| すね | 4 |
| ふともも | 2 |
| 動きやすさ | 5 |
カーボンヒーターはスイッチを入れたらすぐに暖かくなるのが最大の特徴です。
一昔前はすぐ暖かくなる暖房としてハロゲンヒーターもありましたが、カーボンヒーターはハロゲンヒーターよりも発熱効率が良く、電気代は約半分になっています。
それでも他の寒さ対策よりは電気代高めですが。
赤外線で温めるタイプの暖房器具のため、ヒーターの近くの正面だけが暖かくなります。
3時間ほど連続使用していると自動的に電源が切れる製品が多く、消し忘れても安全。
しかし、赤外線に当たっている場所以外は温まらないため、姿勢を維持して勉強を続けるには少し不向きな感じ。
勉強机専用というよりは、リビングやキッチンでも使える暖房器具として使うと良いでしょう。
現在私は事務所に来客があったときに、お客様が寒くないようにカーボンヒーターを使っていますよ。
足元寒さ対策3:デスクパネルヒーター
デスク上部パネルヒーター
| 価格 | 4,000円~ |
| 電気代(1時間あたり) | 3円 |
| 足 | 1 |
| すね | 1 |
| ふともも | 3 |
| 動きやすさ | 5 |
机の天板の裏側に貼り付けるタイプのパネルヒーターです。
電源を入れてから温まるまで少し時間がかかります。
電気代が安く、ふとももあたりをじんわりと温めてくれます。パネルに密着するくらい近いと十分温かいのですが、パネルから10cmくらい離れるとじんわりくらいの暖かさ。
そのため、足やすねの方はほとんど暖房効果が無く寒いです。
体を拘束する要素が一切ないのでとにかく動きやすいのが利点でしょう。
こちらも3時間ほどで自動電源オフになりますが、電源が切れたことに気づきにくいのが難点。
机の天板の材質によっては上手く張り付かず、突然ガタっと落ちてくる場合があります。
使用中に落ちてきてもやけどするような熱さではないんですが、そのくらいの暖房効果なので距離が離れるほど暖房効果は薄くなります。
デスク下置き型パネルヒーター
| 価格 | 4,000円~ |
| 電気代(1時間あたり) | 4円 |
| 足 | 2 |
| すね | 3 |
| ふともも | 1 |
| 動きやすさ | 5 |
机の下のスペースにコの字型に置いて使うパネルヒーターです。
天板の裏側に貼り付けるタイプよりも暖かくなる面が広いので電気代が少しかかります。
貼り付けるタイプとの最大の違いは温める部位です。
ふともも以外はじんわり温めてくれます。
勉強中に足をよく動かす人はパネルヒーターを蹴っ飛ばしてしまう可能性アリ。
足元寒さ対策4:ヒータースリッパ
| 価格 | 2,000円~ |
| 電気代(1時間あたり) | 0.1円~0.3円 |
| 足 | 5 |
| すね | 1 |
| ふともも | 1 |
| 動きやすさ | 3~4 |
ヒーター内蔵のスリッパで足をすっぽり温めてくれます。
足を包み込んでくれるのでかなり温かいです。
しかし、すねからふとももにかけては効果が無いです。
パソコンのUSBから給電できる商品が多いのも特徴ですね。
足を包み込んで温めると結構足に汗をかきます。
そのため、結構足が蒸れるのが難点。また、通常のスリッパよりも裏面が滑りやすいので、履いたまま不意に動こうとするとスリップの危険や、電源コードを引っ張る危険性があります。
スリッパではなく、足を入れるタイプもあります。
こちらはスリップ等の危険は減りますが、勉強中に足を動かせないのが難点。
私は足を入れるタイプのヒータースリッパを使っていましたが、すねとふとももが寒いので結局使うのを止めてしまいました。
スポンサーリンク
足元寒さ対策5:ロング足温器
| 価格 | 9,000円~ |
| 電気代(1時間あたり) | 0.1円~1.4円 |
| 足 | 4 |
| すね | 4 |
| ふともも | 4 |
| 動きやすさ | 1 |
つま先からお腹まですっぽりと履くタイプのヒーターです。
広範囲をまんべんなく温めてくれるのが最大の特徴で、体を包み込んでくれるので温かいです。
しかし、履いたままでは動けないので来客時などにはいちいち脱がなければならず面倒です。また、全体を包んでいるので汗で蒸れるのも難点。
1製品で足元全体を温められるので、勉強に専念でき動かなくても大丈夫な環境であれば暖房効果はかなり高いです。
足元寒さ対策6:電気ひざかけ
| 価格 | 3,000円~ |
| 電気代(1時間あたり) | 0.1円~0.7円 |
| 足 | 2 |
| すね | 4 |
| ふともも | 4 |
| 動きやすさ | 3~4 |
通常のひざかけタイプのものから、着る毛布サイズのものまでバリエーション、デザインが豊富。
温まるまで少し時間はかかりますが、温度調節もしやすく、ひざにかけるだけ、足全体に巻きつける、体全体に羽織るなど状況に合わせて使い分けられるのが特徴です。
急な来客時も電気ひざかけを椅子の上に置いて対応に行けるのでそこそこ動きやすいのが個人的に良く、現在も電気ひざかけを使いながら仕事しています。
足元寒さ対策7:ダンボール+古着
| 価格 | 0円 |
| 電気代(1時間あたり) | 0円 |
| 足 | 2 |
| すね | 2 |
| ふともも | 1 |
| 動きやすさ | 3 |
お金をかけずにできる方法として、ダンボールと古着を活用する方法があります。
机の下にダンボールを置き、その中にもう着ない古着をたくさん入れ、その中に足を突っ込むという方法です。
自分の体温を使って温まることができます。
この方法はやはり足が少し蒸れるのと、ダンボールの大きさで温まる範囲や足の可動域が決まってしまうのが難点です。
ダンボールが高いとひざくらいまで温まれますが、足の出し入れがしにくくなりますし、ダンボールが低いとふくらはぎの途中までしか温まれません。
足元寒さ対策番外:ダイニングこたつ
| 価格 | 数万円 |
| 電気代(1時間あたり) | 5円 |
| 足 | 2 |
| すね | 2 |
| ふともも | 3 |
| 動きやすさ | 5 |
椅子で使うタイプの背が高いこたつです。
勉強机ではなく、こたつテーブルで勉強しようという方法ですね。
実家にこのタイプのダイニングこたつがあったのですが、空間が広いためか通常のこたつよりも内部温度が上がりにくい印象。
使っていると毛布に隙間が空きやすく結構寒かったり。個人的な意見では、通常のこたつで勉強した方がいいかなーと思います。
勉強机・デスクの足元寒さ対策は組み合わせで効果あり
ここまで7つ(+1)の足元寒さ対策を紹介してきましたが、万能な方法はありません。しかし、複数の方法を組み合わせて使うことで温まることも可能です。
例えば、「デスク上部パネルヒーター+ダンボール古着」で足からふとももまでをカバーしたり、「デスク下置き型パネルヒーター+ひざかけ」「ヒータースリッパ+電気ひざかけ」などを組み合わせることも考えられます。
寒さの感じ方は個人差もあるので、特に寒いと感じる部分を温められる方法を選ぶと良いですよ。
冬の勉強机・デスクの足元の寒さ対策のまとめ
長時間勉強する上で、足元の寒さ対策は風邪やインフルエンザ予防のために大切です。
足元を温める製品は以下のように色々ありますが、それぞれ一長一短があります。
- 遠赤外線セラミックヒーター
- カーボンヒーター
- デスクパネルヒーター
- ヒータースリッパ
- ロング足温器
- 電気ひざかけ
- ダンボール+古着
温かさとともに、動きやすさも結構重要なポイントです。あなたの状況に合ったものを選んで勉強を続けられるようにしましょう。
「寒くて勉強するのが嫌だ、億劫だ」と思ってしまったら勉強は進められませんよ!
| 関連記事:「【2023年版】デスクライトで勉強の集中力アップ!おすすめデスクライト4選」 |