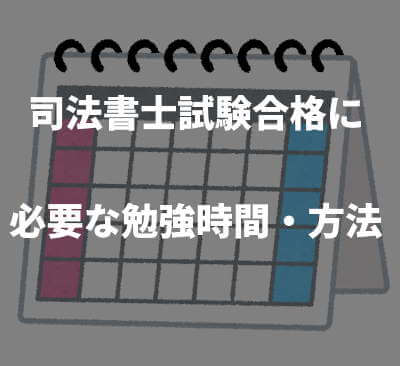おつかれさまです!資格ワン運営の司法書士「よしと」です。

司法書士の難易度は高い?
合格するまでの平均勉強時間、目安はどのくらい?
最短でどのくらいの勉強時間・勉強期間で合格できる?
独学なら勉強時間はどのくらい必要?
どうやって勉強していけば、勉強時間が確保できる?
そんな風に思っていませんか?
私は4年間勉強して司法書士試験に合格しました。
司法書士試験は難易度が高く、合格までに必要な勉強時間もとても多いです。
しかし、勉強時間を増やすことだけを目的にしてだらだらと勉強しても合格はできません。
そのためこの記事では、
|
について解説します。
この記事を読むことで、司法書士試験に合格するまでに必要な勉強時間がどのくらいなのか、毎日どのくらい勉強すれば達成できるのか、どのような勉強方法なら達成できるのかが分かりますよ。
1日に必要な勉強時間が分かれば毎日の生活スタイルを変えることもできます。
正しい受験生活を身につけて着実に司法書士試験合格に必要な力を身につけましょう。
司法書士の難易度はかなり高い
難しい試験であるほど必要な勉強時間は多くなります。
そして、司法書士は試験の難易度がかなり高い資格。
2023年(令和5年度)の司法書士試験データは以下のとおり。
| 受験者数 | 13,372人 |
| 合格者数 | 695人 |
| 合格率 |
5.19% |
| 試験倍率 | 19.24倍 |
法務省:令和5年度(2023年度)司法書士試験の最終結果について
司法書士試験の合格率は5%前後ということからもかなり難易度が高いことが分かります。
合格率と試験倍率を他の法律資格試験と比較すると以下のとおり。
| 試験種 | 合格率 | 倍率 |
| 司法書士試験 | 5.18% | 19.28倍 |
| 行政書士試験(2021) | 10.72% | 9.32倍 |
| 司法試験予備試験 | 3.63% | 27.55倍 |
このように、最高峰の法律資格と言える司法試験予備試験に近い難易度となっています。
実際には司法書士試験と司法試験予備試験のどちらが難しいのか?
という質問がされることがありますが、試験科目の違いや求められる回答方法の違いがあるため「人による」としか言えません。
- 司法書士試験の合格率は5%前後、とても難易度が高い
- 司法書士試験の難易度は司法試験予備試験に近い
司法書士合格までの平均勉強時間は3000時間
司法書士試験に合格するまでの平均勉強時間の目安は3000時間と言われます。
司法書士予備校の1つである辰已法律研究所で指導している松本雅典講師も「平均的な学習時間は3000時間前後」としています。
実際に、私自身が4年間かけて合格したときの勉強時間も約3000時間。
このように司法書士試験は3~4年で3000時間勉強するのが合格する目安です。
しかし、勉強時間=3000時間というのは目安にしか過ぎません。3000時間勉強したからといって確実に合格できるわけではないので注意。
中には倍の6000時間勉強しても合格できないという人もいます。
司法書士試験に合格するには、勉強時間を増やすだけではなく「勉強時間」と「勉強効率」を両立させるのがコツです。
|
このように勉強効率を高めている人であれば、3~4年で3000時間勉強することで司法書士試験に合格できる可能性は高いですよ。
- 「3~4年で3000時間」が合格までに必要な平均勉強時間の目安
- 司法書士試験合格には「勉強時間」と「勉強効率」の両立が大事
「勉強がすごく苦手」「5~6年の長期受験を予定している」などのようにあなたの条件が変われば合格に必要な勉強時間の目安も変わります。
勉強時間の目安は3000時間とは言いますが、それよりも短い勉強時間で合格する人ももちろんいます。
実際に短期間で司法書士試験に合格している人がどのくらいの勉強時間で合格しているのかを探っていきましょう。
最短合格したいなら1日の勉強時間は10時間以上
司法書士試験に1年未満で合格している人も確かにいます。
ある程度信憑性がありそうな最短合格体験としては以下の2人が有名。
|
山本講師は自身の短期合格のノウハウを元にした司法書士テキスト「山本浩司のオートマシステム」の著者であり、「オートマ」は分かりやすいと人気が高く、独学の定番テキストになっています。
一方の松本講師も短期合格の勉強の方法論として「司法書士5ヶ月合格法」という本を書いています。
司法書士テキスト「リアリスティック」の著者でもあり、「リアリスティック」も分かりやすいという評判が多い良テキスト。
松本講師は辰已法律研究所の司法書士講座の看板講師として活躍中です。
松本講師が5ヶ月で司法書士試験に合格したときには、1日17時間勉強していたと言います。
普通の人が真似することはとてもできないでしょう。
他の短期合格者の合格体験記を見てみると、6~7ヶ月の間毎日10時間以上勉強していたという話がよく見られます。
半年間毎日10時間勉強していたとすると、勉強時間は合計1800時間。
このあたりが最短合格ラインと言えそうです。
最短合格を目指す場合の勉強方法はとても単純。
- 予備校の講義を受ける
- 講義・テキストの復習をする
- 過去問を解く
- 1~3を毎日繰り返す
これだけです。
多くの講師がそのように指導し、多くの受験生がこの勉強方法で合格をしてきました。
私ももっと勉強時間こそかけていますが、この方法に従って合格しています。
- 司法書士試験に最短合格したいのなら、半年で1日10時間勉強くらい必要
- 勉強時間だけでなく、効率も良くなければ短期合格はできない
- 一定以上の勉強効率にするために、予備校を使うことを推奨
短期合格者ほど合計勉強時間は少ない?
私が合格するまでの勉強時間は4年で3000時間でしたが、超短期合格者の勉強時間は半年で1800時間くらいです。
短期合格者ほど勉強時間が短く済んでいる理由は、時間経過で忘れる知識量が減り、覚え直すために勉強を繰り返す回数が少なくなるからです。
私の実際の経験と、超短期合格者の実例を元に、「合格までの勉強期間」「合計勉強時間」「1日の平均勉強時間」「1週間の勉強時間」を計算すると以下のとおり。
| 勉強期間 | 必要勉強時間 | 1日の平均勉強時間 | 1週間の平均勉強時間 |
| 半年 | 1800時間 | 9時間50分 | 68時間51分 |
| 1年 | 1971時間 | 5時間24分 | 37時間48分 |
| 1年半 | 2142時間 | 3時間54分 | 27時間21分 |
| 2年 | 2314時間 | 3時間10分 | 22時間11分 |
| 2年半 | 2485時間 | 2時間43分 | 19時間3分 |
| 3年 | 2657時間 | 2時間25分 | 16時間59分 |
| 3年半 | 2828時間 | 2時間12分 | 15時間29分 |
| 4年 | 3000時間 | 2時間3分 | 14時間23分 |
| 4年半 | 3172時間 | 1時間55分 | 13時間30分 |
| 5年 | 3343時間 | 1時間49分 | 12時間49分 |
| 5年半 | 3514時間 | 1時間45分 | 12時間15分 |
| 6年 | 3685時間 | 1時間40分 | 11時間46分 |
1日に2~3時間勉強できれば、2~4年ほどで合格を狙えます。
このあたりが普通の人でも実現可能な勉強時間でしょう。
長期計画で勉強しても、日々忘れる知識量も増えるため、1日あたりの勉強時間は2時間前後からあまり減少しません。
時間をかけても司法書士試験に合格したいなら、1日平均2時間以上は勉強できるようになる必要があります。
独学なら「+1000時間以上」は勉強時間が必要
独学は予備校に比べてどうしても勉強効率は落ちます。
そのため、独学だと司法書士試験合格までに必要な勉強時間も増えてしまいます。
独学する場合の勉強時間は、予備校を使う場合の勉強時間+1000時間が目安。
勉強が苦手な人だと+2000時間は必要になることも。
独学だと特に「初めて勉強するところ」の理解に時間がかかるため勉強効率が悪くなります。
予備校の講義を聴かずにテキストを読むのであれば、1ページ理解するのに5分前後余計に時間がかかると考えると+1000時間となるのです。

勉強は苦手、繰り返し読まないと理解が進まない!
という人であれば、1ページ理解するのに予備校の講義よりも10分多くかかるかもしれません。
そうすると合格までの勉強時間は+2000時間。
それなりに順調に独学できた場合でも、合格までには相当の時間がかかります。

3000時間近く勉強したけれど合格できそうな点が取れない
という独学者は予備校の初学者向け講座で知識を整理し直した方が良いかもしれません。
実際に12年の独学から予備校に切り替えたおかげで3年で合格した人もいます。
伊藤塾:独学12年から予備校3年で合格した例
![]() ただでさえ難しい司法書士試験ですから、これから勉強を始めようと考えている人は、試験範囲を一通り理解するためだけでも予備校を使うことをおすすめします。
ただでさえ難しい司法書士試験ですから、これから勉強を始めようと考えている人は、試験範囲を一通り理解するためだけでも予備校を使うことをおすすめします。
- 独学は勉強効率が悪くなるので+1000時間以上必要
- 勉強が苦手な人なら+2000時間以上必要になる場合も
- 一通り理解するまでだけでも予備校で効率よく勉強した方が良い
科目別の勉強時間のかけ方
司法書士試験は全部で11科目から出題がありますが、出題数や問題の難易度に違いがあるため勉強時間の配分を考える必要があります。
司法書士試験11科目の出題数と配点は以下のとおり。
| 午前(2時間) | 択一 | 憲法 | 3問 | 配点:9点 |
午前択一 合計35問 105点満点 |
| 民法 | 20問 | 配点:60点 | |||
| 刑法 | 3問 | 配点:9点 | |||
| 会社法・商法 | 9問 | 配点:27点 | |||
| 午後(3時間) | 択一 | 民事訴訟法 | 5問 | 配点:15点 |
午後択一 合計35問 105点満点 |
| 民事執行法 | 1問 | 配点:3点 | |||
| 民事保全法 | 1問 | 配点:3点 | |||
| 供託法 | 3問 | 配点:9点 | |||
| 司法書士法 | 1問 | 配点:3点 | |||
| 不動産登記法 | 16問 | 配点:48点 | |||
| 商業登記法 | 8問 | 配点:24点 | |||
| 記述 | 不動産登記法 | 1問 | 配点:70点 |
記述 合計2問 140点満点 |
|
| 商業登記法 | 1問 | 配点:70点 |
科目内でもどの分野から何問出題されるのか、といった一定の傾向もあります。
この出題数に対して、どのように勉強時間を配分すれば良いのかについて説明していきます。
主要4科目が勉強時間の80%以上
「民法」「不動産登記法」「会社法・商法」「商業登記法」は出題数が多く、まとめて主要4科目と呼ばれます。
択一式試験の出題数割合は主要4科目で75.7%ですが、勉強時間割合は80%以上かける必要があります。
その理由は以下の2つ。
| 主要4科目に80%以上の勉強時間を配分する理由 |
|
主要4科目は択一式でも細かいところまで問われることが多いので、出題数以上に時間をかけて深く勉強しましょう。
科目ごとの特徴に合わせて効率よく勉強
主要4科目以外をまとめて「マイナー科目」と呼ぶことが多くあります。
科目によって1~5問出題されるので、多く出題される科目はそれだけ多く勉強時間を使うことになります。
しかし、同じ1問しか出題されないマイナー科目であっても、テキストや過去問の重要性が違うために、同じ時間をかけて勉強すれば良いものではないです。
科目ごとの特徴を押さえ、効率良く勉強することで勉強時間を短縮できる科目もあるので、マイナー科目はメリハリをつけて勉強するのが重要です。
- 科目ごとの難易度の違いがあるので、勉強時間の配分は考える必要あり
- 主要4科目に出題数割合以上の勉強時間(80%以上)をかける
- マイナー科目は科目ごとの特徴を把握して、勉強時間配分にもメリハリをつける
合格から逆算して勉強計画を立てる

司法書士試験に合格するには勉強時間3000時間が必要だと言われてもどうやって勉強していけば良いのか想像がつかない
という人も多いと思います。
1年以内での最短合格を目指すのであれば、

なりふり構わず起きている間はずっと勉強!
というような勉強方法になります。
しかし、最短合格にこだわらずに勉強するなら、司法書士試験合格に必要な勉強時間3000時間から逆算していくとどのような勉強をすれば良いのかイメージがしやすいです。
実際に合格から順番に逆算して、1日どのくらい勉強すれば良いのかを確認してみましょう。
1年で1000時間勉強しよう
私が合格後の新人研修で名刺交換をした人たちは、3~6回くらいの受験回数で合格した人が多くいました。
順当に勉強できれば3年、私を含めて「途中、勉強で失敗したな~」という経験がある人はそれに加えて合格まで数年経っているという感じです。
あなたはもちろんしっかり勉強してなるべく早く司法書士試験に合格したいと考えているでしょうから、3年間で合格するとしておきましょう。
3年間で司法書士試験に合格しようと思うと、1年で1000時間勉強しなければなりません。
この「1年で1000時間勉強」が1つの目標です。
逆算すると1日の勉強時間は平均3時間
「1年で1000時間」でもまだ具体的な勉強のイメージには繋がりません。
1日あたりに直すと平均2.74時間勉強が必要なことになります。
盆も正月も休みなく勉強を続けられるのであれば、1日平均3時間勉強をしていけば1年で1000時間、3年で3000時間勉強して司法書士試験に合格できることになります。
1日平均3時間勉強なら、専業で勉強している人であればかなり現実的な計画です。
|
は必ずあるものですから、専業で勉強しているなら1日4~5時間勉強を目標としておけば多少勉強できなかった日があっても、結果的に1日の平均勉強時間を3時間以上にすることができるでしょう。
問題は忙しい社会人。
社会人が毎日3時間勉強するのはかなり難易度が高いです。
勉強をかなり頑張れる人でも平日は平均2時間ぐらいが現実的でしょう。
そのため、忙しい社会人は4年で勉強時間3000時間を目指し、1年で750時間、平日は1日に2時間勉強するほうが余裕のある司法書士試験合格計画となります。
- 3年で3000時間、1年で1000時間、1日3時間と逆算して勉強時間をイメージ
- 専業なら1日4~5時間を目標に勉強すると結果的に1日平均3時間くらいになる
- 社会人は平日1日あたり2時間、4年で3000時間を目指したほうが余裕がある
ケース別の1日あたりの勉強時間や、私が合格するまでの1日の勉強時間については以下の記事で詳しく解説しています。
| 関連記事:「司法書士になるには勉強時間は1日どのくらい必要か【合格者の経験】」 |
社会人が勉強時間を確保する方法・手順
社会人が働きながら勉強するのであれば、1日3時間勉強するのはかなり大変。
しかし、1日2時間でも決して簡単ではありません。
そのため、社会人は勉強時間をどう確保するかが問題となります。
社会人が勉強時間を確保する方法には以下のようなものがあります。
|
それぞれの方法について説明をしていきます。
方法1:1日の無駄な時間を勉強時間に変える
勉強時間を増やすための最初の手順は、1日の中の無駄な行動を止めて勉強時間に変えることです。
「すぐに止められる行動」だけでなく「できれば止めたくない行動」も勉強時間に変えていけると社会人でも十分な勉強時間を確保できます。
1日の行動の分類の仕方や、「できれば止めたくない行動」を勉強時間に変える具体的な方法・手順については以下の記事で詳しく解説しています。
| 関連記事:「【たった4手順】勉強する時間がない人が勉強時間を増やす方法」 |
また、1日にスマホを触る時間が長い人なら、スマホに触る時間を短くして勉強時間を増やすのが良いでしょう。
| 関連記事:「勉強中にスマホを触らない10の方法【受験生の集中できないを解消】」 |
スマホを触る時間が長いのであれば、次の「方法2」でも説明するように、スマホで効率良く学べる「スタディング」のような予備校を選ぶのも手です。
方法2:隙間時間でも勉強できる工夫をする
勉強時間を増やすには、昼休憩や電車を待つ時間などのちょっとした隙間時間にも勉強することも効果的。
お手軽なところではスマホで使える過去問アプリで勉強するのが良いでしょう。
| 関連記事:「【無料】司法書士の「過去問+解説」アプリで分野別に対策!」 |
予備校の中には「スタディング」のように、スマホで過去問が解けるだけでなく、スマホで講義が受けやすい通信講座もあります。
|
といった特徴も嬉しい点。
しかし、スマホで勉強しやすい反面、他の予備校と比べると講義時間が少なめという特徴もあるので、対策法も含めてあなたに合うかは慎重に判断しましょう。
方法3:通信講座で講義を倍速消化、通学時間カット
講義の中の無駄な間や、勉強の準備に余計な時間をかけないために通学の予備校ではなく、通信講座を利用することで勉強時間を増やすこともできます。
Web通信講座であれば
|
といったことができ、勉強時間を増やすだけでなく勉強効率も上がります。
電車の中で講義音声を聴いて復習するなど、隙間時間の活用にも効果がありますので、あなたに合う通信講座を選ぶと司法書士試験に短期合格しやすくなります。
方法4:あなたの環境を大きく変えて時間を作り出す
社会人が勉強時間を増やすための方法には色々ありますが、どうしても仕事が忙しくて勉強する時間がないという人もいるでしょう。
そういった人は、職場が近くなるように引っ越し、あるいはもっと時間に余裕がある職業に転職、といった環境を大幅に変えることが司法書士試験の合格に一番必要かもしれません。
司法書士試験は中途半端な状態でだらだら勉強していると10年経っても合格できない、なんてことにもなりかねません。
勉強時間が確保できないのであれば
|
といった選択が必要になるでしょう。
合格できなければ司法書士試験の勉強をする意味が薄いので、あなたの優先順位に応じて選んでください。
| 関連記事:司法書士と補助者の転職&求人情報を探す8つの方法【未経験でも】 |
司法書士試験合格に必要な勉強時間と勉強法のポイントまとめ
司法書士試験の合格する勉強時間の目安は3000時間。
これは、予備校を使ってある程度効率よく勉強できる人の目安です。
独学するのであれば+1000時間以上の勉強時間が必要となるでしょう。
人によっては2000時間、さらにそれ以上時間がかかるケースもあるので、これから勉強を始めるのであれば予備校を使っておいたほうが良いです。
実際に12年の独学から予備校に切り替えたおかげで3年で合格したというケースも。
あなたが司法書士試験に合格するためには、合格に必要な勉強時間から逆算して1日の勉強時間を決めましょう。
実現可能性の高い勉強計画は以下の2つです。
| 合格目標 | 1年の勉強時間 | 1日の平均勉強時間 |
|
3年で合格する (専業で勉強できる人向け) |
3000÷3=1000時間 | 1000÷365=約3時間 |
|
4年で合格する (働きながら勉強する人向け) |
3000÷4=750時間 | 750÷365=約2時間 |
忙しい社会人が合格に必要な勉強時間を確保するためには以下のような方法が考えられます。
|
どうしても必要な勉強時間の確保が難しいのであれば、司法書士を諦めるというのも手です。
司法書士試験はテキスト、過去問、模試を定番通りの方法で正しく勉強していけば、勉強時間およそ3000時間で合格することができます。
これは法学部出身ではない私自身でも実証していますし、他にも多くの人が3000時間くらいで合格しています。
しかし、勉強をしない期間があったり、自分の判断で勉強する量を減らしてしまったりすれば時間だけかけても合格することはできません。
司法書士試験の合格を目指すのであれば、あれもこれもと自分に都合の良い意見だけをつまみ食いせず、自分に合った予備校の指導方法に合わせて一貫した勉強を続けるのが一番です。
そのためには自分に一番合う予備校を選ぶことがベストですよ!