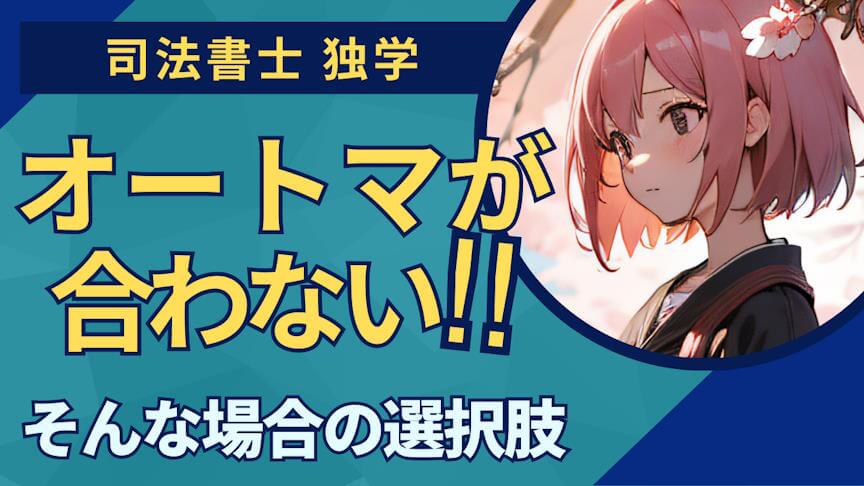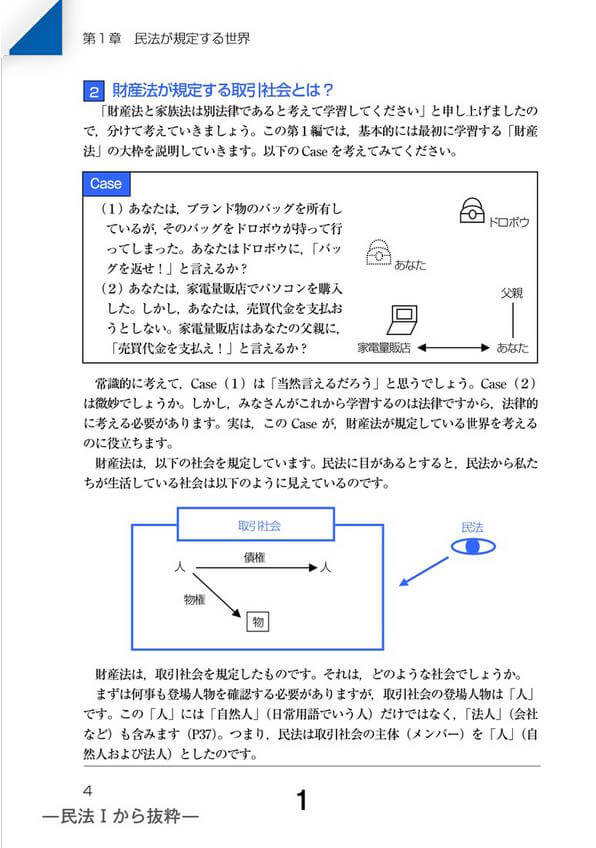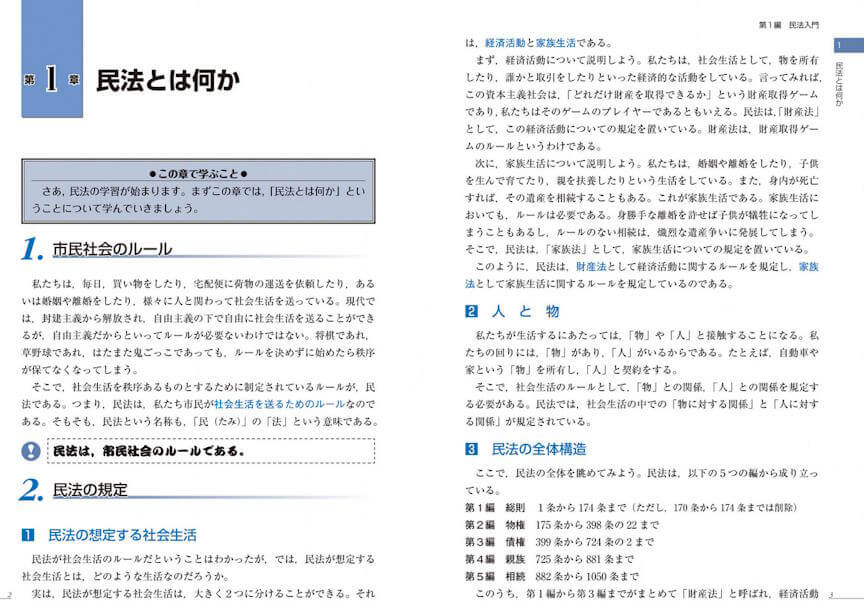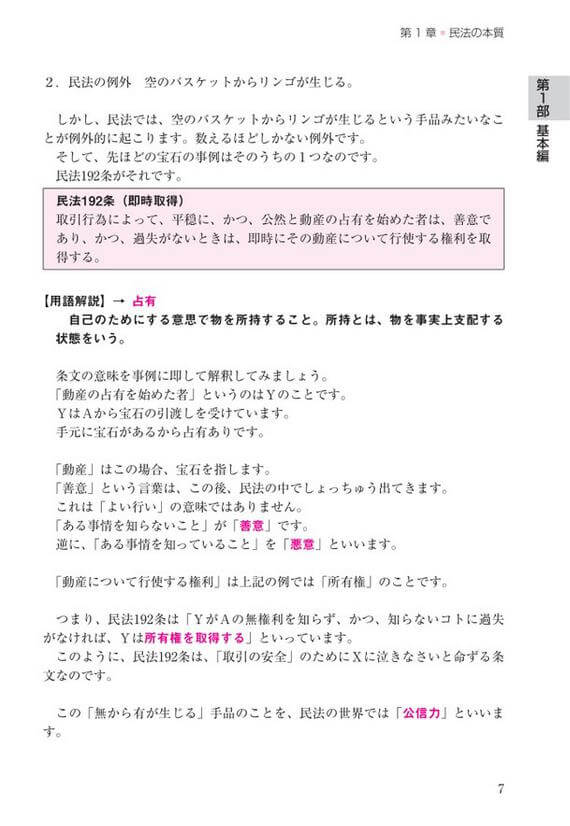おつかれさまです!資格ワン運営の司法書士「よしと」です。

司法書士を独学するために「オートマ」を買ったけど、どうにも自分には合わない…
オートマが合わないならリアリスティックとかに乗り換えるべき?
そんな風に思っていませんか?
司法書士の試験は独学で挑戦する人も多いですが、その中で一つの大きな課題となるのがテキストの選択。
特に、司法書士試験の独学では「オートマ」の人気が高いです。
しかし、オートマがあれば必ずしも合格できるとは限りませんし、なかにはオートマが合わないと感じる人もいます。
そのため、この記事では
|
について具体的に解説します。
また、その上で
|
についても説明していきます。
実際にオートマを使って勉強を始め、4年間かけて司法書士試験に合格した私が解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
司法書士テキストのオートマは合わない人もいる
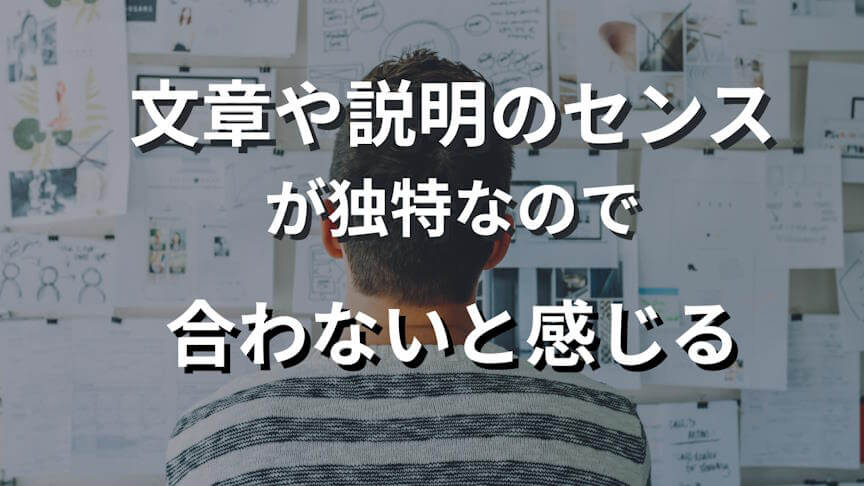 オートマはTAC(Wセミナー)の山本浩司先生が書いた司法書士試験テキストです。
オートマはTAC(Wセミナー)の山本浩司先生が書いた司法書士試験テキストです。
司法書士の独学ではオートマは1番人気のテキストですが、合わないと感じる人もいます。
そのため、ここでは独学する場合のオートマの使い方を確認し、なぜオートマが合わないと感じるのか理由を解説していきます。
オートマの使い方
オートマは講義をしているような「ですます調」で書かれているテキストです。
|
なども入っているのも大きな特徴。
そのため、オートマを読み物として読んでいくだけで、難しい法律用語の意味などが分かるほか、問題演習もできるため自然とアウトプットもできます。
|
この2つを交互にやるのは司法書士に限らず、資格試験の定番勉強法。
オートマだけでインプットとアウトプットの両方ができるので、司法書士の独学でオートマを使う場合は、最初から順番に読み進めて行くだけで良いんです。
オートマの過去問だけ完璧にすれば合格できる?
オートマには参考問題として過去問が載っており、アウトプットもできるのが利点です。
著者の山本浩司先生は、オートマだけ読んで勉強すれば合格できるようにオートマを作成しましたが、普通の人はオートマだけで合格することは難しいです。
オートマに載っている過去問は数が少ないため、
|
といった「とても頭の良い人」「応用力のある人」でなければ本試験の様々な問題に答えられるようにはなれないでしょう。
実際に、オートマで独学合格したという人のほとんどがオートマ以外の教材を併用しています。
そのため、普通の人はオートマと一緒に過去問題集も解きましょう。
オートマシリーズとして刊行されている選択肢別の「オートマ過去問」
本試験と同じ五肢択一形式の「合格ゾーン」
など色々な過去問がありますが、どの過去問を使っても合格に問題はないため、出題形式や解説の書き方などの好みで選んで大丈夫です。
オートマは文章中で参考問題が出題されていますので、そのタイミングでそこまでの説明に対応する過去問も解くようにすればOK。
オートマを「回す」
司法書士試験に合格するためには、択一式試験でおよそ80%以上の正答率が必要です。
オートマが分かりやすく、記憶に定着しやすいテキストであっても1度や2度読んだくらいでは、80%以上の正答率を出すことは難しいです。
司法書士試験に合格するためには、オートマをもう一度最初から読み直すことを何度も何度も繰り返して、オートマの内容ならほぼ100%理解して覚えた!という状態にする必要があります。
このように、オートマの中身を覚えるまで何度も繰り返し読み直すことを「回す」と言います。
オートマを回すときは、単に読むだけでなく目的意識を持って読みましょう。
例えば、
| 1周目 | 細かい部分は分からなくても良いので、全体の流れを掴む (理解度20~30%でOK) |
| 2周目 | もう一度最初から理解し直すつもりで読む (理解度20~50%) |
| 3周目 | 分かっているところは流して、よく分からないところをじっくり読む (理解度40~60%) |
| 4周目 | 分かっている部分も細かい所まで覚えていく。 (理解度50~80%) |
| 5周目 | この先にどんな内容が書いてあるのか、先回りで思い出しながら読む。 (理解度60~90%) |
みたいなイメージです。
オートマを回しているときは、1周目と同じように過去問も一緒に回すほうが覚えやすくなります。
オートマプレミアはいらない
オートマシリーズには「オートマプレミア」というテキストもあります。
オートマが初学者向けのテキストであるのに対して、オートマプレミアは中上級者向けのテキストとなっています。
しかし、前述したように司法書士試験に合格するためにはオートマを回せば良く、オートマを読み終わった後にオートマプレミアを買う必要はありません。
なぜなら、オートマプレミアは
|
という特徴があるテキストだからです。
オートマプレミアは、科目を横断した知識の関連付けや、応用力を身につけることも目的としています。
オートマを合格に必須の基礎とするなら、オートマプレミアは応用であり、司法書士試験に合格に必須の内容ではありません。
実際に私は「オートマ」と「オートマプレミア」の両方を使っていましたが、最終的にはオートマを回して合格しています。
オートマは難しい?合わない人がいる理由

オートマが分かりやすいと言われたのに、読んでみたら難しくて分からない。
なんだか自分には合わなくて分かりづらい。
そう感じる人もいます。
オートマが難しい、合わないと感じる理由としては以下のようなものが考えられます。
| 理由 | 対策等 |
| 説明が易しくても、司法書士試験向けのため覚える内容のレベルが高く難しい。 | 試験内容が難しいのでテキストも難しいのは仕方がない。 合格者(私)も最初は読んでも分からない部分がたくさんあったので最初は難しくて当然。繰り返し読む内に少しずつ分かるようになってくる。 |
| 学校で使ってきた教科書と違ってフランクな言葉で書かれているので、頭が勉強モードに切り替わらず覚えられない。 | 固いテキストのほうが勉強しやすい人は、学校のようにテキストを開きながら講義を聴くほうが勉強効率が良い。 |
| 分かりやすく説明するための例え話の内容が古く、理解・共感できない。 | 例えがハマらなかったらスルーして、重要な部分だけ覚えるようにしましょう。 例え話は本筋ではないので、苦手なら飛ばしてOKです。 |
| まとめ表や比較表のようなものが少なく、覚えられない | 表でまとまっていると「覚えている」「理解できている」つもりになってしまいます。 そのため、掲載されている表を覚えるよりも、繰り返し読むうちに「自分でまとめ表等を書ける」ようになるのが試験的には望ましいです。 |
万人に好かれる人がいないように、オートマも万人向けではありません。
どうしてもオートマが合わないと感じる場合には他の選択肢も検討しましょう。
司法書士の独学でオートマが合わない場合の選択肢
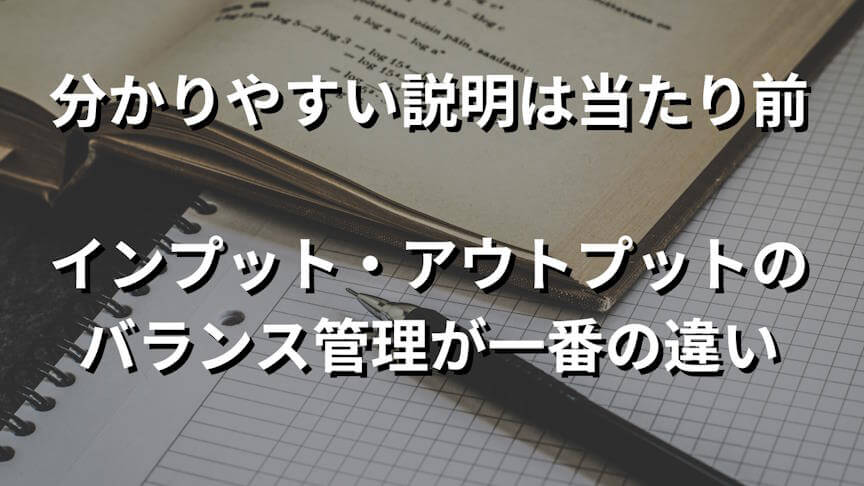 オートマが合わないと感じる人のために、他のテキストで独学するのはどうなのか、どうしてもオートマが合わない場合にはどうすれば良いのかについて以下の順番で説明していきます。
オートマが合わないと感じる人のために、他のテキストで独学するのはどうなのか、どうしてもオートマが合わない場合にはどうすれば良いのかについて以下の順番で説明していきます。
|
リアリスティックの人気も高い
独学ではオートマの次に名前が挙がるのが「リアリスティック」。
リアリスティックは辰已法律研究所の松本雅典先生が書いた司法書士試験テキストです。
リアリスティックも分かりやすい詳しい説明に定評があります。
砕けすぎない言葉づかいですが、ですます調で比較的読みやすいです。
実際にリアリスティックで独学合格したという人もいますので、オートマが合わない人の選択肢になります。
Vマジックという選択肢もある
最近は司法書士試験テキストとして「Vマジック」の名前が挙がることも増えました。
VマジックはLEC(東京リーガルマインド)の森山和正先生が書いた司法書士試験テキストです。
テキストで森山先生の講義を再現し、分かりやすく説明されている点は同じですが、オートマやリアリスティックとの大きな違いは文体です。
オートマやリアリスティックが読みやすさを重視した「ですます調」で書かれているのに対して、Vマジックは「だ・である調」で書かれています。
森山先生は「ですます調で分かりやすさや取っつきやすさを演出せず、本試験と同じだ・である調で学習したほうが知識と問題文が結びつき合格しやすい」として、あえてだ・である調でテキストを作成しています。
従来の学校で使うような教科書っぽいテキストのほうが逆に読みやすいタイプの人は、Vマジックを使用するのもアリでしょう。
オートマかリアリスティック、どっちで独学するのが良い?
司法書士試験の独学でオートマが合わないと感じる場合、リアリスティックやVマジックに乗り換えたほうが良いのでしょうか?
リアリスティックやVマジックも良いテキストですが、独学用途なら多少我慢してでもオートマを回したほうが良いです。
合わないと感じてもオートマで独学したほうが良い理由は以下のとおり。
|
オートマは独学のために作られており、知識のインプットと問題演習のアウトプットをバランス良く、適切なタイミングでできます。
しかし、リアリスティックやVマジックは知識のインプット専門になるため、自分で適切なタイミングを考えて過去問演習をする必要があります。
この「過去問を解くタイミングを考えること」は勉強センスが必要で、誰にでもできることではありません。
実際に、松本先生のリアリスティックを使用した講座では、講義ごとに解くべき必須の過去問が毎回指示されます。
リアリスティックは松本先生の講義と合わせて完成されるものであり、テキストだけで独学することを想定しているテキストではないのです。
その点、オートマは過去問演習ができるだけでなく一目見たときの分かりやすさ、読みやすさでも群を抜いています。
オートマは強調部分が「赤紫」で目をひくので、回していても重要部分が必ず目に入り読み飛ばすことがありません。
また、1文をなるべく短くまとめ、細かく改行されているので、文章の意味や流れを理解しやすくなっています。
このような点から講義を受けずにテキストで独学するのであれば、多少オートマが合わないと感じたとしてもオートマを使うべきと言われるのです。
「リアリスティックやVマジックは文章がギュッと詰められているため、必要な補足や知識を書き込むのであれば、直前期に回す優良なテキストになります。そのため、松本先生や森山先生の講義を受けるのであればぜひ使うべきテキストです。
しかし、独学でテキストを回す場合には、重要部分の見落としやテキストに偏重して必要な過去問演習が不十分になる可能性が高まるため、教科書らしいテキストを使って勉強することに慣れている人でないと合格は難しいでしょう。」
上記の文章はリアリスティックやVマジックと同じくらいの文字の詰め込み具合で書いてみました。
この文章が読みづらい、もっと短い文章の方が良い、もっと改行を入れて欲しいと感じる人は、オートマで独学するほうがベターです。
実際に、独学合格者のブログなどを調べてみるとほとんどの人がオートマを使っています。
一部には、
- リアリスティック+合格ゾーンで合格した人
- 司法試験用テキスト+合格ゾーンで勉強して過去問をほぼ全問解けるようにして合格した人
もいますが、確認できたのはそれぞれ1人ずつだけ。
オートマ以外を独学教材としておすすめしているのは、
|
というパターンも多いです。
独学合格者の中ではオートマが圧倒的に人気ですので、独学用であればオートマ以外を選ぶのはリスクが大きいのが現状です。
オートマがどうしても合わない、無理な場合
ここまでの説明のようにあなたが司法書士試験を独学するのであれば、多少オートマが合わないと感じてもオートマを使うのがおすすめです。
しかし、どうしても合わない、オートマを読むのがもう無理という人もいるでしょう。
その場合は、独学を諦めてオートマ以外のテキストを使用している講座を受講しましょう。
他のテキストでの独学は合格例が極端に少ないため、あなた自身が勉強法を一から確立しなければなりません。
司法書士試験の勉強をするだけでなく勉強法も自分で考えだすことは、特別頭が良かったり、能力が高い人でなければできません。
知識のインプットと問題演習のアウトプットの適切なタイミングも教えてくれるオートマを使わないのであれば、
インプットとアウトプットを指導してくれる予備校・通信講座を使い、あなたが司法書士の勉強だけに専念できるようにするのがおすすめです。
幸いなことに予備校の費用や講義時間などは非常に多彩になってきているので、あなたの希望に合う講座は昔に比べて見つけやすくなっています。
【司法書士】オートマが合わない人はどう独学するべき?まとめ
この記事では、司法書士テキストのオートマの使い方やその効果、オートマが合わないと感じる人がいる理由を解説しました。
オートマが合わない場合の選択肢として、リアリスティックやVマジックなどのテキストの特性も挙げて比較しました。
しかし、独学に限って言えば多少合わないと感じてもオートマを使うのがおすすめです。
オートマは単に説明が分かりやすいだけでなく、読み進めていくだけで適切なインプットとアウトプットをタイミング良くこなせます。
どうしても個人の学習スタイルや理解力、相性などに違いがあるため最適な勉強法は人によって異なります。
それでも独学合格者のほとんどがオートマを使っていたことは事実ですし、さらに言えば司法書士試験の合格者はほとんどが講座の利用者です。
あなたがどうしてもオートマが合わないと感じるのであれば、オートマ独学は諦めてインプットとアウトプットの両方をこなせる講座を利用するのが合理的でしょう。
アガルート(1日1~3時間勉強できる人向け)
なので、勉強に挫折せずに続けやすく、しっかり合格が目指せる。 12回払いまでの分割手数料が0円に
合格時の全額返金制度あり |
スタディング(1日1時間前後勉強できる人向け)
なので、忙しく勉強時間の確保が難しい人でも合格を目指せる。 無料体験
|