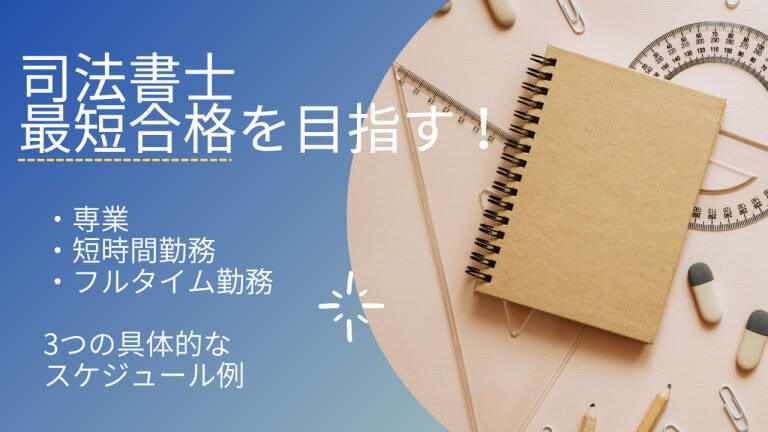おつかれさまです!資格ワン運営の司法書士「よしと」です。

司法書士になるべく早く、最短合格したい!
最短で合格するにはどうやって勉強すれば良い?
社会人が最短合格するにはどうすれば良い?
そんな風に思っていませんか?
司法書士の勉強をするからには、できるだけ早く、最短合格したいですよね。
しかし、司法書士試験はとても難しい試験です。
必要な勉強量や勉強方法を把握しないまま、なんとなく勉強していたら最短合格どころか10年経っても合格できない可能性もあります。
そのため、この記事ではこれから司法書士の勉強を始める人、もう既に勉強を始めている人が、司法書士に最短合格するための以下の内容について説明します。
|
私自身は司法書士試験合格まで4年かかりました。
試験に合格してみると「あの勉強法は役に立った」「あの勉強はいらなかった」という部分が見えてきます。
その経験から、最短合格するためにはどのくらい勉強しなければいけないのかを具体的に1日のタイムスケジュール例を示しながら詳しく解説していきます。
司法書士の最短合格はどのくらいかかるか
あなたが司法書士試験に最短どのくらいで合格できるのかは、あなたが毎日どのくらい勉強できるかによって変わります。
ケース別に最短合格期間をまとめると以下のとおり。
|
司法書士の最短合格までの期間 |
||
| ケース | 毎日・毎週の勉強時間 | 最短合格期間 |
| ①勉強に専念できる場合 |
理想 毎日10時間勉強 |
10ヶ月 |
|
現実 毎日6時間勉強 |
1年5ヶ月 | |
| ②短時間勤務の場合 |
理想 毎週60時間勉強 |
1年 |
|
現実 毎週30時間勉強 |
2年 | |
| ③フルタイム勤務の場合 |
理想 毎週40時間勉強 |
1年6ヶ月 |
|
現実 毎週20時間勉強 |
3年 | |
理想的なケースは、最短合格記録保持者レベルのもので普通の人が真似できるものではないと考えてください。
|
理想的なケースを実践できる人に必要なもの |
|
この3つ全てが揃った人でないと理想的なケースを実践するのは難しいです。
一方、普通の人でも現実的なケースの方で頑張ればその人なりの最短合格を目指すことができます。
理想的なケースと比べると大分楽ですが、現実的なケースもかなり頑張らないと実践できない難易度。

これからは趣味を我慢して勉強するぞ!1ヶ月に1日くらいは息抜きに好きなこともやろう
くらいの覚悟が必要です。
趣味の時間はほとんど無くなると考えておきましょう。
- 「趣味も大事だから」
- 「毎日少しだけなら」
- 「毎週少しだけなら」
という気持ちが今の時点であるなら残念ながら最短合格はきっとできません。
最短合格するための勉強時間は上記のとおりですが、間違った勉強法をすれば合格まで遠回りになり最短合格できなくなってしまいます。
そのため、次は最短合格するための勉強法について説明します。
司法書士に最短合格するための勉強法

司法書士に最短合格するための勉強法は非常にシンプル。
- 予備校の講義を受ける
- 講義の復習をする
- 講義の範囲の過去問を解く
- 毎日繰り返す
基本的にこれを地道に繰り返していくだけ。
司法書士試験はたくさんの浅い知識があるよりも、100%正確な知識がどれだけあるかが重要な試験。そのため、習ったことを徹底的にマスターする勉強法が最短合格への近道です。
| 講義→復習→過去問 → 次の講義→復習→過去問→・・・ |
この繰り返しです。
講義が無い日については、「復習→過去問」で勉強するようにしましょう。
司法書士試験は合格までに同じ内容を2回、3回、4回…と繰り返し勉強することになるので、勉強がまだ進んでないうちでも習った部分を何度も復習して過去問を解くのが有効です。
過去問や復習をいい加減にやって、「基本から勉強範囲を広げる」方法は多くの受験生がやってしまう定番失敗事例。(私も経験あり)
過去問と復習を徹底して、今使っているテキストと過去問を100%にすることを目標とした方が最短合格しやすいですよ。

独学じゃ最短合格は目指せないの?

最短合格を目指すのであれば独学はおすすめしません。
なぜなら、予備校で勉強内容、勉強方針、勉強のペースを調節してもらいながら勉強する方が、安定して成績を伸ばすことができるからです。
独学だとその人の優秀さによって「合格できる」「合格できない」の差が大きく、合格までにかかる期間の幅が広くなってしまいます。
1日の勉強量にもよりますが独学する場合は、2年~10年以上かかります。
独学と予備校の差のイメージは以下のような感じ。
|
独学と予備校の差のイメージ |
|
| 独学 | 予備校 |
| 来年のフルマラソン出場・完走に向けて一人でトレーニングをする。 | 来年のフルマラソン出場・完走に向けて、プロトレーナーに食事、練習などのサポートをしてもらいながらトレーニングをする。 |
| 羅針盤だけを用意して太平洋横断を目指す。 | GPS、レーダーなどの設備を用意し、海の変化に応じて方針を決めてくれるプロ船長と一緒に太平洋横断を目指す。 |
イメージとしてこのくらいの違いがあります。

独学で一発合格したという人もいますが、毎日起きている間はずっと勉強していたり、1日12時間以上勉強した上に運も必要だったりします。
不可能ではありませんが、おすすめはできません。
試験データと私が試験合格者と話した経験を合わせると、独学合格者はかなり甘く見積もっても司法書士試験受験者のおよそ0.3%ほどしかいないという計算になります。
独学はおろか予備校を使った場合でも、誰でも短期合格できる!とは言えません。
司法書士試験はそのくらい難しいと思っておきましょう。
また、(過去の私のように)忙しい社会人ほど、

平日は勉強できない日もあるけど、休日にまとめて勉強してカバーする!
という勉強計画を立てる人がいますが、経験上おすすめしません。
なぜなら、
|
の2つであれば、毎日2時間勉強の方が
|
といった利点があるので司法書士に最短合格しやすくなります。
忙しい人も、毎日短時間で良いので勉強する習慣を身につけるのが最短合格のコツです。
続いては、司法書士に最短合格するためのテキストや過去問など教材の選び方について解説します。
テキストと過去問の選び方
司法書士試験に最短合格するためには、
|
司法書士最短合格のためのテキスト・過去問の選び方 |
|
| テキスト | 予備校の講義で使うテキストを使う |
| 過去問 |
予備校で付いてくる過去問があればそれを使う。 自分で買う場合は「オートマ過去問」を買って使う。 |
とするのがおすすめ。
司法書士に最短合格しようと考えるなら、余計なテキストや過去問を買う必要はありません。
なぜなら前述のとおり、司法書士試験は勉強範囲を広げるよりも今勉強している内容を確実に身につける方が大事だからです。
そのため、まず予備校で用意されるテキストや過去問をしっかりとやりきるようにしましょう。
予備校によっては過去問が付いていない場合もあるので、その場合は「オートマ過去問」を買うのがおすすめです。
オートマ過去問には以下のような特徴があります。
|
「オートマ過去問」の特徴 |
|
これらの特徴があるため、最短合格を目指して短時間で効率よく勉強するには最適な過去問になっています。
オートマ過去問は科目ごとに全9冊あります。
オートマ過去問のほか、電車移動や昼休みなどの隙間時間にもコソ勉できるよう、過去問アプリもインストールしておくと無駄なく過去問演習ができます。
使っているテキストが分かりにくい場合
予備校で使うテキストがどうしても自分に合わず、理解しづらい場合には独学の一番人気テキスト「山本浩司のautoma system(通称:オートマ)」で苦手部分を勉強しましょう。
「オートマ」シリーズはTAC/Wセミナーの山本浩司講師が著者の独学定番テキストで、具体例も多く分かりやすいテキストとして有名です。
「オートマ」を全て揃えようとすると結構お金がかかってしまいますが、苦手部分だけであればそこまでの出費にはなりません。
そのため、予備校の講義で詰まったら追いつけなくなる前に「オートマ」で復習をして理解を確実なものにするのも良いです。
記述式の勉強で詰まった場合
予備校の講義やテキストで記述式がよくわからない場合には、伊藤塾の山村拓也講師が著者の記述式で人気の市販テキスト「うかる!司法書士記述式答案構成力」で解法を勉強しましょう。
記述式の解法は講師によって違いがあるため、あなたにとって最適な解法に出会うためにいくつかの解法を試してみると良いです。
「うかる!司法書士記述式答案構成力」シリーズも独学合格者が記述式の勉強によく利用している定番テキストです。
予備校の選び方
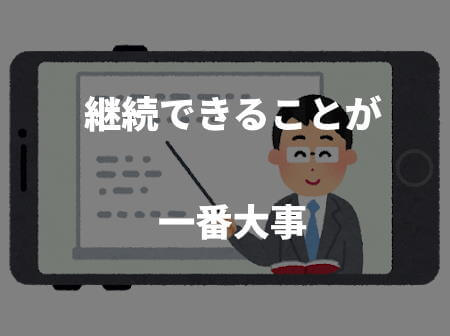
司法書士に最短合格するためには、あなたに合った予備校を選ぶ必要があります。
なぜなら、予備校での勉強が嫌になってしまったら最短合格どころか合格自体が難しくなってしまうからです。

予備校選びで一番大事なのは「講師との相性」。
次に大事なのは通学や通信などの「学習スタイル」です。
|
といった「あなたが勉強しやすい講師」。
|
といった「学習スタイル」。
この2つを選んで毎日勉強を続けることが最短合格には必要です。
一定レベル以上の予備校であれば司法書士合格に必要な知識は学べるので、勉強の続けやすさを重視して予備校を選べば大丈夫。
講師との相性や学習スタイルなどの、あなたの勉強のしやすさを重視してしっかりとやりきりましょう。
働きながらで勉強時間の確保に不安がある人は、通学よりも通信講座を選ぶのがおすすめ。
特に勉強時間が無い人は、講義が短時間であり、通勤時間や昼休みなどの隙間時間にもコツコツ勉強のしやすいWeb通信講座専門がベター。
同じWeb通信専門でも
|
のように特徴に違いがあるのであなたに合った講座を選びましょう。
予備校、テキスト、過去問、それぞれどれを使うかが決まればあとは勉強をしていくだけ。
具体的に毎日どのように生活して勉強していくのか具体例を見ていきましょう。
司法書士最短合格の勉強スケジュール3種類
司法書士に最短合格するまで、ケース別に具体的なスケジュール例を挙げていきます。
この具体例を元に、

私だとこの勉強法はできなさそう。

私ならもっと勉強できるから、より短期で合格できるかも!?
など、あなたが最短合格を目指す場合にどういう生活を送っていくのかイメージしてください。
|
に分けて説明していますので、あなたが該当する部分だけ読めばOKです。
勉強に専念(専業)のケース
勉強に専念できる場合の最短合格は以下のとおりと説明しました。
| ケース | 毎日・毎週の勉強時間 | 最短合格期間 |
| 勉強に専念できる場合 |
理想 毎日10時間勉強 |
10ヶ月 |
|
現実 毎日6時間勉強 |
1年5ヶ月 |
実際にこの通り勉強しようとすると、毎日の生活イメージは以下のようになります。
理想的な(毎日10時間勉強)ケース
10ヶ月間、毎日10時間勉強する場合の1日のタイムスケジュール例は以下のとおり。
| 07:00 | 起床 |
| 07:00~07:30 | 朝食等 |
| 07:30~11:30(4時間) | 勉強(講義) |
| 11:30~12:30 | 昼食等 |
| 12:30~16:30(4時間) | 勉強(復習) |
| 16:30~18:30 | 休憩等 |
| 18:30~19:30 | 夕食等 |
| 19:30~21:30(2時間) | 勉強(過去問) |
| 21:30~23:30 | 休憩等 |
| 23:30 | 就寝 |
勉強の合間に適宜休憩を取ったり、他の用事を片付けたりするため「休憩等」で確保している自由時間はもっと少なくなります。
自由な時間はずっと勉強しているような感じになるでしょう。
こんな生活を10ヶ月続けて最短合格できる人はかなり稀だと考えられます。
現実的な(毎日6時間勉強)ケース
1年5ヶ月間、毎日6時間勉強する場合の1日のタイムスケジュール例は以下のとおり。
| 07:00 | 起床 |
| 07:00~07:30 | 朝食等 |
| 07:30~09:00 | 自由時間 |
| 09:00~12:00(3時間) | 勉強(講義) |
| 12:00~13:00 | 昼食等 |
| 13:00~14:00 | 休憩等 |
| 14:00~16:00(2時間) | 勉強(復習) |
| 16:00~18:30 | 休憩等 |
| 18:30~19:30 | 夕食等 |
| 19:30~21:00 | 自由時間 |
| 21:00~22:00(1時間) | 勉強(過去問) |
| 22:00~23:30 | 休憩等 |
| 23:30 | 就寝 |
一見、自由時間や休憩等の時間が多いようにも見えますが、それらの時間で家事や買い物、毎日習慣にしている運動等をすると結構ギリギリになるでしょう。
しかし、こんな感じのスケジュールで勉強を続けられれば最短合格に必要な勉強時間は確保できます。
短時間勤務のケース
短時間勤務は、「週5日4時間ほど勤務し、2日は休日」という状態を想定します。
実際にはそれよりも仕事が多い、少ないという事情があると思いますので目安としてご覧ください。
この勤務形態の場合の最短合格は以下のとおりと説明しました。
| 司法書士の最短合格期間 | ||
| ケース | 毎日・毎週の勉強時間 | 最短合格期間 |
| 短時間勤務の場合 |
理想 毎週60時間勉強 |
1年 |
|
現実 毎週30時間勉強 |
2年 | |
実際にこの通り勉強しようとすると、毎日の生活イメージは以下のようになります。
理想的な(週60時間=平日8時間、休日10時間)ケース
1年間、毎週60時間勉強する場合の1日のタイムスケジュール例は以下のとおり。
| 平日 | 休日 | ||
| 07:00 | 起床 | 07:00 | 起床 |
| 07:00~07:30 | 朝食等 | 07:00~07:30 | 朝食等 |
| 07:30~08:00 | 出勤等 |
07:30~11:30 (4時間) |
勉強(講義) |
| 08:00~12:00 | 勤務 | 11:30~12:30 | 昼食等 |
| 12:00~12:30 | 退勤等 |
12:30~16:30 (4時間) |
勉強(復習) |
| 12:30~13:30 | 昼食等 | ||
|
13:30~18:30 (5時間) |
勉強(講義、復習) | 16:30~18:30 | 休憩等 |
| 18:30~19:30 | 夕食等 | 18:30~19:30 | 夕食等 |
|
19:30~22:30 (3時間) |
勉強 (復習、過去問) |
19:30~21:30 (2時間) |
勉強(過去問) |
| 22:30~23:30 | 休憩等 | 21:30~23:30 | 休憩等 |
| 23:30 | 就寝 | 23:30 | 就寝 |
平日は残業があったり、他にやることがあると実現できないほどタイトなスケジュールになります。
ちょっと残業やトラブルがあるだけで成り立たなくなるので現実味が薄くなっています。
現実的な(週30時間=平日4時間、休日5時間)ケース
2年間、毎週30時間勉強する場合の1日のタイムスケジュール例は以下のとおり。
| 平日 | 休日 | ||
| 07:00 | 起床 | 07:00 | 起床 |
| 07:00~07:30 | 朝食等 | 07:00~07:30 | 朝食等 |
| 07:30~08:00 | 出勤等 | 07:30~09:00 | 自由時間 |
| 08:00~12:00 | 勤務 |
09:00~11:00 (2時間) |
勉強(講義) |
| 12:00~12:30 | 退勤等 | 11:00~12:00 | 自由時間 |
| 12:30~13:30 | 昼食等 | 12:00~13:00 | 昼食等 |
| 13:30~14:30 | 休憩等 | 13:00~14:00 | 休憩等 |
|
14:30~17:30 (3時間) |
勉強(講義、復習) |
14:00~16:00 (2時間) |
勉強(講義、復習) |
| 17:30~18:30 | 休憩等 | 16:00~18:30 | 休憩等 |
| 18:30~19:30 | 夕食等 | 18:30~19:30 | 夕食等 |
| 19:30~20:30 | 自由時間 | 19:30~21:00 | 自由時間 |
|
20:30~21:30 (1時間) |
勉強 (復習、過去問) |
21:00~22:00 (1時間) |
勉強(過去問) |
| 21:30~23:30 | 休憩等 | 22:00~23:30 | 休憩等 |
| 23:30 | 就寝 | 23:30 | 就寝 |
平日は自由時間等をフル活用すれば多少家事もできそうです。かなり大変ですが。
休日にある程度時間があるので、平日に食べるおかずをまとめて作っておいたりなどの準備をすることになるでしょう。
そのため、2年での最短合格を目指す場合でも相当な努力を継続する必要があります。
フルタイム勤務のケース
フルタイム勤務は、「週5日8時間勤務し、2日は休日」という状態を想定します。
フルタイム勤務の場合の最短合格は以下のとおりと説明しました。
| 司法書士の最短合格期間 | ||
| ケース | 毎日・毎週の勉強時間 | 最短合格期間 |
| フルタイム勤務の場合 |
理想 毎週40時間勉強 |
1年6ヶ月 |
|
現実 毎週20時間勉強 |
3年 | |
実際にこの通り勉強しようとすると、毎日の生活イメージは以下のようになります。
理想的な(週40時間=平日4時間、休日10時間)ケース
1年6ヶ月間、毎週40時間勉強する場合の1日のタイムスケジュール例は以下のとおり。
| 平日 | 休日 | ||
| 07:00 | 起床 | 07:00 | 起床 |
| 07:00~07:30 | 朝食等 | 07:00~07:30 | 朝食等 |
| 07:30~08:00 | 出勤等 |
07:30~11:30 (4時間) |
勉強(講義) |
| 08:00~12:00 | 勤務 | ||
| 12:00~13:00 | 昼食等 | 11:30~12:30 | 昼食等 |
| 13:00~17:00 | 勤務 |
12:30~16:30 (4時間) |
勉強(復習) |
| 17:00~17:30 | 退勤等 | ||
|
17:30~18:30 (1時間) |
勉強(講義) | 16:30~18:30 | 休憩等 |
| 18:30~19:30 | 夕食等 | 18:30~19:30 | 夕食等 |
| 19:30~22:30 | 勉強(講義、復習、過去問) |
19:30~21:30 (2時間) |
勉強(過去問) |
| 22:30~23:30 | 休憩等 | 21:30~23:30 | 休憩等 |
| 23:30 | 就寝 | 23:30 | 就寝 |
平日は仕事と勉強以外のことをする時間はありません。
少し残業があったり、通勤時間が多くかかるだけで破綻します。
平日は通勤中(電車)で勉強できる環境が必須になるでしょう。
休日も決して余裕があるわけではないので、1年6ヶ月毎日これだけ忙しくてもやりきるだけの気力、体力、環境が不可欠であり現実にはかなり厳しいことが分かると思います。
現実的な(週20時間=平日2時間、休日5時間)ケース
3年間、毎週20時間勉強する場合の1日のタイムスケジュール例は以下のとおり。
| 平日 | 休日 | ||
| 07:00 | 起床 | 07:00 | 起床 |
| 07:00~07:30 | 朝食等 | 07:00~07:30 | 朝食等 |
| 07:30~08:00 | 出勤等 | 07:30~09:00 | 自由時間 |
| 08:00~12:00 | 勤務 |
09:00~11:00 (2時間) |
勉強(講義) |
| 12:00~13:00 | 昼食等 | 11:00~12:00 | 自由時間 |
| 13:00~17:00 | 勤務 | 12:00~13:00 | 昼食等 |
| 13:00~14:00 | 休憩等 | ||
| 17:00~17:30 | 退勤等 |
14:00~16:00 (2時間) |
勉強(講義、復習) |
| 17:30~18:30 | 休憩等 | 16:00~18:30 | 休憩等 |
| 18:30~19:30 | 夕食等 | 18:30~19:30 | 夕食等 |
| 19:30~20:30 | 自由時間 | 19:30~21:00 | 自由時間 |
|
20:30~22:30 (2時間) |
勉強(講義、復習、過去問) |
21:00~22:00 (1時間) |
勉強(過去問) |
| 22:30~23:30 | 休憩等 | 22:00~23:30 | 休憩等 |
| 23:30 | 就寝 | 23:30 | 就寝 |
平日に仕事と勉強以外の時間が少しだけあるので、最低限の家事をしたり家族とコミュニケーションを取ることが可能になります。
それでも平日の勉強がなかなか進まないので、通勤時間や昼休みなども活用して勉強をしたいところです。
休日も午前か午後に勉強時間を固めることも可能ですので、午前午後のどちらかだけであれば家族サービスなどをすることも可能でしょう。
フルタイムで勤務しながら司法書士の最短合格を目指すのであれば、このような生活がギリギリ現実的な範囲ではないかと思います。
フルタイム勤務の現実的なケースのように、平日2時間の勉強時間を確保するのが難しいとても忙しい人は、スマホで受講・復習・問題演習ができ、1講義が5~15分で隙間時間を勉強時間にできるスタディングの活用がおすすめです。
電車移動や昼休み、夜寝る前などのちょっとした時間を勉強時間に変えればコツコツと勉強時間を増やせます。
司法書士の最短合格を目指す勉強スケジュールまとめ
勉強に専念できるのか、短時間勤務をしているのか、フルタイム勤務なのかケース別に司法書士に最短合格する期間を計算すると以下のようになります。
|
司法書士の最短合格までの期間 |
||
| ケース | 毎日・毎週の勉強時間 | 最短合格期間 |
| ①勉強に専念できる場合 |
理想 毎日10時間勉強 |
10ヶ月 |
|
現実 毎日6時間勉強 |
1年5ヶ月 | |
| ②短時間勤務の場合 |
理想 毎週60時間勉強 |
1年 |
|
現実 毎週30時間勉強 |
2年 | |
| ③フルタイム勤務の場合 |
理想 毎週40時間勉強 |
1年6ヶ月 |
|
現実 毎週20時間勉強 |
3年 | |
1日の具体的なスケジュールを考えると、理想的なケースを実践できる人はかなり少ないと考えられます。
普通の人がかなり頑張っても現実的なケースで勉強するのが最短合格への道だと言うことができるでしょう。
具体的な勉強法は単純です。
|
講義が無い日は復習と過去問をひたすら繰り返すだけです。
これ以外の特別なことをする必要はありません。
最短合格を目指す場合には、他の余計なことをやっている余裕はないと言うこともできます。
テキストや過去問は予備校の講義に付いているものを使い込むのが第一です。
過去問が付いていない講座の場合、最短合格のためにはWセミナー山本浩司講師の「オートマ過去問」を買うことをおすすめします。
講義やテキストで理解するのが難しく、予備校の講義に遅れてしまいそうな場合には独学の人気テキスト「オートマ」で苦手部分だけ補うのがおすすめ。
記述式で行き詰まった場合には、「オートマ記述式」は難易度が高いので伊藤塾山村拓也講師の「うかる!司法書士記述式答案構成力」で勉強してみるのが良いです。
利用する予備校は「講師との相性」次点で「学習スタイル」を重視して、勉強が続けやすいところを選ぶようにしましょう。
現実的なケースであってもその通りに毎日勉強を続けるのは非常に困難です。
しかし、一方でそれだけの勉強を頑張って続けられれば合格できる可能性が高いのが司法書士試験。
途中で勉強プランが崩れてしまった場合、最短合格することはできないでしょう。
しかし、最短合格にこだわらなければ合格を目指すことはまだまだ可能です。
最短合格を目指して頑張って勉強したことは無駄にはなりません。
もし最短合格できなかったとしても、数年後の合格に役立ちます。
あなたが毎日勉強するスケジュールを無理なく立てられるなら、計画的に司法書士試験合格を目指せるでしょう。
それだけの苦労をして司法書士を目指したいかどうかよく考えて、司法書士の勉強をするのか、どうやって勉強するのかを選んでくださいね。