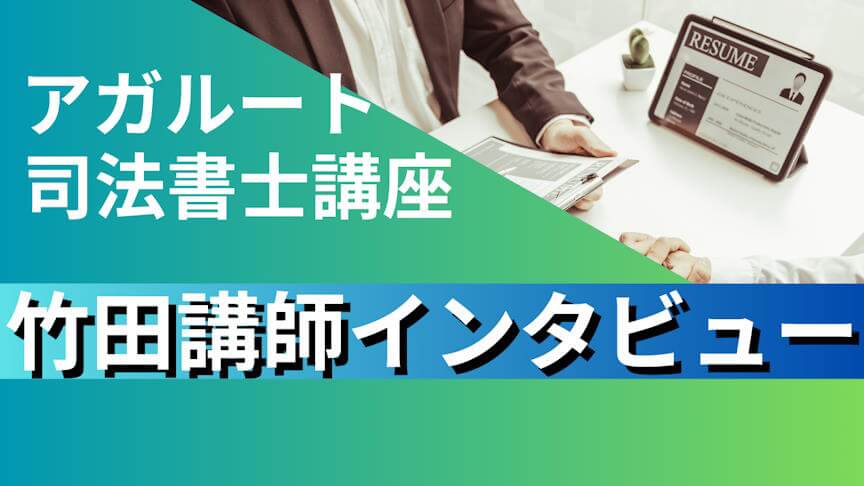おつかれさまです!資格ワン運営の司法書士「よしと」です。

アガルートの司法書士講座ってどうなんだろう?
公式サイトに載っている以上の情報は無いかな?
そんな風に思っていませんか?
司法書士講座は高額な買い物になりますから失敗できません。
そのため、実際に4年かけて司法書士試験に合格している現役の司法書士が、アガルートアカデミー司法書士講座の竹田講師にインタビューしてお話を伺いました。
少しでも多くの情報を入手して、ぜひ、あなたの講座選びの参考にしてください。
アガルート司法書士講座の講師にインタビュー
 今回はアガルートの司法書士講座について、以下の10項目の質問をしてきました。
今回はアガルートの司法書士講座について、以下の10項目の質問をしてきました。
|
質問1:入門講座で初学者向けに工夫している点は?

アガルートの入門総合カリキュラムは司法書士試験の学習が初めての方向けとされていますが、
初学者のためにアガルートが工夫している点は具体的にどのようなものがありますか?

入門総合カリキュラムは法律初学者を対象としていますから、講義では基礎的なことから丁寧に説明しています。
法律用語は初学者にとって決して馴染みのあるものではありません。
そのため、専門書に出てくるような言葉の使い方ではなく、誰でも分かるような簡易な言葉を用いて講義が行なわれます。

また、担当されている浅野講師はオリジナルレジュメを豊富に使用し、視覚に訴えるかたちで分かりやすく教えることに定評があります。
実際の登記簿謄本のサンプルなども使用し、できるだけ受講生の皆さんがイメージしやすいように工夫をしています。
- 基礎的なことから丁寧に説明
- 馴染みのない法律用語ではなく、誰でも分かる簡易な言葉を使う
- 文章だけでなく、視覚に訴えるかたちで講義
質問2:大手と比べ、アガルート司法書士講座の強みはどこですか?

いわゆる大手と呼ばれるような予備校も色々な司法書士講座を開講していますが、
大手予備校と比べて、アガルートの司法書士講座の強みはどのような点だと自負していますか?

まず挙げられるのは、講座全体のボリュームです。
【大手予備校の講座】
は、基幹講義だけで400時間近くもあります。
それ以外に答練などの回数も相当量があり、受験専念者や時間に融通が利く仕事の人でなければ、こなすことが難しいのが現実です。
「司法書士試験には興味があるけれど、最後までやれる自信がない」
と、受講を断念される方も多数いらっしゃることかと思います。

それに対し、
【アガルートの講座】
は入門の講義であっても約300時間ほどです。
答練や記述講座など、その他の講座を含めても、仕事と兼業の方が十分にこなすことができる量になっています。
もちろん、合格に必要な知識量はすべて含まれています。

2点目としましては、コスト面です。
【大手予備校の司法書士講座】
は質は非常に良いと思いますが、一方で費用もそれなりに高額です。
司法書士試験は合格までに平均3~5年はかかります。
仮に大手予備校の講座を5年間取り続けるとすれば、数百万円を予備校に支払うことになります。

その点
【アガルートの講座】
は過度な負担にならずに受講いただける金額かと思います。
【アガルート公式サイト】の
キャンペーン割引済みの講座費用一覧はこちら ![]()

入門講座で料金を比較すると、
| 大手予備校 | 定価約44万円~ (別途過去問題集を買う必要あり、入会金など必要な場合あり) |
| アガルート2025年目標 入門総合カリキュラムライト |
定価約24万円 (テキスト・過去問込み) |
ですから確かに費用は45%以上安くなります。
私自身、大手を4年受講していたので100万円以上は費用がかかってしまいました。
質問3:兼業受験生でもアガルートのボリュームについていける?

アガルートの入門者向け講座には、
- 入門総合講義
- 入門総合カリキュラムライト
- 入門総合カリキュラムフル
の3種類がありますが、
入門総合講義だけでも323時間とかなりボリュームがあります。
司法書士試験は仕事をしながら勉強する兼業受験生も多いですが、そういった兼業受験生でもついていけるのでしょうか?
どのくらいの期間、1日どのくらい勉強して合格することを想定されていますか?

先にお伝えした内容と重なりますが、大手予備校の講義時間数は400時間ほどですから、300時間程度というのは司法書士受験対策講座としては、決して長くはありません。
司法書士試験は全11科目もあり、合格率5%の難関試験ですから、最低限これくらいの講義量は必要になります。

アガルートの入門講座は最長2年間で学習することができます。
1日平均1時間の視聴時間があれば、総合講義すべてを視聴するまでに1年かかりません。
実際、アガルートには兼業受講生が多いのですが、講義時間が負担になるというご意見をいただいたことはありません。

最長2年の受講期間があれば、1日平均1時間勉強の人でも
- 最初の1年で講義を全部視聴できる
- 残り1年あれば復習や過去問もガッツリできる
という感じですね。
早く勉強を始めるほど復習や過去問に時間を使えますし、少し遅れてスタートしても1日2時間とか頑張れば追いつけるのは現実的な戦略かも。
質問4:アガルート司法書士講座の講師陣について

アガルートの入門者向け講座では、
- 竹田 篤史講師
- 浅野 勇貴講師
のお二人の講師のほか、近年は
- 海老澤 毅講師
- 三枝 りょう講師
のお二人も加わりました。
竹田講師から見て、各講師が得意としていること、すごいと思うことや、講師が増えたことによってできるようになったことなどについて教えてください。

私以外の先生はすべて司法書士実務家でもありますから、実務にも非常に明るいです。
司法書士試験は実務家登用試験と言われるほど実務に近い試験ですから、実務における知識も豊富な講師陣は大変魅力的かと思います。

また、近年加入された三枝先生、海老澤先生は講師歴20年以上の大ベテランです。
長年のご経験から、受講生がハマりやすい箇所や陥りやすい罠を熟知しておられます。
お互いの情報を共有することで、より精錬された講座をつくることが出来るのは、講師が増えたことによる強みかと思います。

ベテラン講師が増えたことはやっぱり安心感につながります。
講師が増えて
- 質問・定期カウンセリングなどのサポートは講師が直接対応
- 新たに択一セルフチェックWebテスト開始
など、確かに講座内容の充実も図られていますね。
アガルート司法書士講座の入門講座を担当する4名の講師について簡単にまとめると以下のとおり。
| 浅野勇貴 講師 | 平成27年合格で群馬県司法書士会の常任理事、日本司法書士会連合会の委員なども務める。図表を多く使って覚える作業をできるだけ省力化する講義が持ち味だが、冗談を交えたしゃべりも結構達者。入門総合講義のほか、記述式上位合格の経験を活かして記述過去問解説講座も担当。 |
| 海老澤毅 講師 | 大手予備校の辰已法律研究所の元講師。司法書士試験指導歴30年にわたる大ベテラン。直前期対策講座全般を担当。 |
| 竹田篤史 講師 |
行政書士・社会保険労務士・司法書士の3つの資格試験に合格。大手予備校で受講相談・教材制作・講師をしていた経験あり。その経験から定期カウンセリングやホームルームを担当。 |
| 三枝りょう 講師 | 大手予備校LECで7年、クレアールで4年、その後小泉司法書士予備校、資格スクエアで講師をしてきた司法書士試験指導歴20年にわたるベテラン。司法書士登録からも10年経っており、現在は東京司法書士会の理事もしている。主に中上級者向けの演習総合講義を担当しているが、初学者向けのホームルームも担当。 |
質問5:アガルートのテキストについて

アガルートのテキストは図表を使って視覚的に分かりやすいようにまとめようとしているだけでなく、文章についても、条文や判例を要約した簡潔な記載となっているように見えます。
その反面、そのような結論になる理由や理解するための道筋を説明する文章はあまり無い構成になっていると感じました。
このように要点を凝縮するタイプのテキストにした狙いや理由はどのようなものでしょうか?

誤解を恐れずに言いますが、司法書士試験は法的論理力を問う試験ではなく、知識を問う試験であるためです。
この点を理解していない方が非常に多いと思います。
この試験に合格するために必要なものは、何よりも「正確な知識」であり、どう考えたかではありません。
司法書士試験は、主に択一式の試験ですから、問題の正誤を正確に判断する必要があります。

テキストは、そのために押さえる必要がある知識を端的に伝える構成となっています。
必要とされる知識を素直に正確に押さえることこそ、短期合格に必要な要素です。

理解を深めるための説明は試験では出ないのは事実ですからね。
市販テキストと違い、講義とセットになることが前提のテキストですから、
- 理解を深めるのは講義
- 必要な知識を過不足なくカバーするのはテキスト
と役割を分けているわけですね。
司法書士試験は範囲が広いので、全て説明を載せると直前期に読めない分厚いテキストになってしまいます。
要点を簡潔にまとめたタイプのテキストは、直前期のまとめノート代わりにしやすいのは利点です。
質問6:アガルートの過去問題集はなぜ肢別形式?

アガルートではテキストだけでなく、講座に過去問題集も付属しています。
確か行政書士講座などでは五肢択一形式の過去問題集だったと思いますが、司法書士講座は肢別形式の過去問題集になっています。
肢別形式を採用した理由はどのようなものでしょうか?

個人的には過去問はどちらのタイプでも良く、使いやすい方を使えば良いと思っています。
私の場合、受験の際にアガルートと同様肢別形式の過去問を使用していました。
【肢別形式】
の利点は、一肢ごとに正確な回答が求められるため、知識の定着につながるという点です。

【五肢択一形式】
の過去問題集の場合、繰り返し解いていると、正解番号を覚えてしまいます。
実は正解番号を記憶しているだけで、知識が定着しているわけではない、ということになりがちです。
肢別の過去問集であれば、そのような心配がなく、正答率の上昇とともに確実に知識の定着を図れます。

私は五肢択一形式の過去問で勉強して合格したタイプです。
でも、確かに選択肢ごとに検討してみると間違えている場合がちょくちょくあり、組み合わせで解けちゃって理解できた気になっていることがあったんですよね。
そのため、私は選択肢ごとにバラバラにまとめノートに書き出し、自分用に肢別問題集を作っていました。
今から勉強するなら最初から肢別過去問題集を使うのはアリですね。
質問7:短答セルフチェックWebテストの詳細は?

2025年度合格目標の総合カリキュラムでは、
2024年1月から新たに「短答セルフチェックWebテスト」
が開始されますが、こちらはどのくらいの頻度、1回あたりどのくらいボリュームで行われるのでしょうか?
問題を後で繰り返し解くことはできるのでしょうか、
また、他の受講生と比較した順位付けなどはされるのでしょうか?

こちらは只今作成中のため、詳細をお答えすることは難しいのですが、およそ単元ごとに各10問程度を想定しています。
あくまで自習用のものですから、順位付けはされません。
繰り返し解くことはもちろん可能です。

過去問を全部解くとなるとかなり大変ですが、単元ごとに10問程度なら、軽い復習問題のような感じで解けますね。
セルフチェックWebテストを解いて理解度をチェックし、間違えた部分や分からなかった部分を復習すると弱点も補えそう。
短答セルフチェックWebテストを含む
【アガルート公式サイト】の入門総合カリキュラムの説明はこちら ![]()
質問8:令和4年度の合格率17.8%となった要因は?

アガルート受講生アンケートでは、令和4年度司法書士試験の合格率が17.8%とされています。
合格率5%ほどの司法書士試験で、合格率17.8%と高い合格率を出せた要因はどういったものだと考えられていますか?

アンケートの集計結果では、令和4年度の合格率は17.8%でした。
合格は受講生の努力の賜物ですから、特に秘訣があるわけではありません。

しかしながら、網羅率の高いテキストを作成していることが、毎年大勢の合格につながっているかと思います。
また、定期カウンセリングをご利用いただいた方の中から短期合格者が出ていることは嬉しい限りです。

あくまで受講生の努力が第一である、ということは私の受験経験でも感じます。
アガルートの受講生には相対的に努力を惜しまない人が多かったのかも。あえて大手を選ばなかった人たちですからハングリー精神がありそうです。
アガルートの「定期カウンセリング」は有料(税込み110,000円)ですが、
- 月1回30分
- 電話で相談
- 単なる合格者ではなく講師が直接対応
などの特徴があります。
2025年合格目標講座では、無料でも月1回15分の「学習カウンセリングチューター」も利用できます。
質問9:孤独になりがちな通信講座でのフォロー制度について

アガルートに限らず合格者の体験談を読んでいると、
通信講座は
- 「時間効率が良かった」
通学講座は
- 「直接質問できて良かった」
- 「直接相談できて良かった」
といった内容が多く見受けられます。
アガルートは通信専門ですが、こうした直接質問、直接相談に対してはどのように考えられていますか?

アガルートには様々なフォロー制度があり、それらを利用して講師に直接質問することができます。
講義や過去問の内容についての質問はもちろん、勉強の仕方、モチベーションに関する相談など、自由に質問をすることができます。
回答はすべて講師が直接行っておりますから、安心してご利用いただけます。

通信講座でも講師が直接質問や相談に回答してくれるのは、回答の正確性だけでなくモチベーションにも影響ありますね。
全体構造編で司法書士の勉強方法のオリエンテーションをしたり、ホームルーム配信をしたりなど、通信でも受講生を孤独にさせない通学講座のようなフォローを目指している印象があります。
質問10:学習カウンセリングチューターと定期カウンセリングの違いは?

入門総合カリキュラムでは、学習相談として
- 月1回15分の「学習カウンセリングチューター」
- 有料オプションで月1回30分の「定期カウンセリング」
がありますが、この2つはどのように違うのでしょうか?
「定期カウンセリング」があった方が良い人、「定期カウンセリング」が無くても大丈夫な人はどのような人でしょうか?

いずれも講師に直接質問することができるものですが、
【定期カウンセリング】
の方が時間が長い分(各回30分)、細かいところまでアドバイスをすることができます。
受験期間は長期に及びます。
その中で、予定どおりに進まないことや転勤、家族の介護など不測の事態が生じることもしばしばあります。
定期カウンセリングでは、そのような話題に至ることもあります。
人生相談の様になるわけですが、皆様からは
- 「話を聴いてもらえてすっきりしました。」
- 「毎回のカウンセリングでモチベーションが上がります」
というお声をいただきます。

また、定期カウンセリングでは毎回次回までの学習の目安をお伝えしています。
それをペースメーカーとすることで、学習を最後まで続けることができます。
独力で通信講座を進めていくことに不安を感じる方は、定期カウンセリングを検討されると良いと思います。

一方、講義と教材だけあれば、後はご自身で進められるというタイプの方は、無料の学習カウンセリングチューターのみで十分です。

相談では最初に質問や状況を伝えるところから始まるので、それで5分くらいは経っちゃうんですよね。
その場合、30分枠があれば回答する時間は倍以上長くなるので、細かいところまでアドバイスできると。
今現在の自分の状況に合った勉強方法について、その都度相談したいなら定期カウンセリングを使ったほうが良さそうな感じ。

今回はインタビューの機会をいただき、ありがとうございました!
アガルート司法書士講座の講師にインタビューまとめ
今回は講師に直接インタビューできるということで、アガルートの司法書士講座サイトを見るだけでは分からない部分を中心に質問してきました。
実際に講義やテキストがあなたに合うかどうかは、講座選びで重要な要素です。
公式サイトから無料体験を申し込むと、
|
といったメリットがありますので、テキストや講義画面の使い勝手を体感できます。

実際にアガルートを受講してみたら、テキストや講義画面が自分に合わなかった。

他の通信講座にしてしまったが、アガルートの無料体験をしてみたらこっちのほうが良かった。アガルートにしておけばよかった。
と後悔しないためにも、一度無料体験して比較検討すると良いでしょう。
また、アガルートの無料受講相談は【Zoom】【電話】【メール】で
|
といった相談ができるので、自分の環境で司法書士試験合格を目指せるのか不安を感じている人も利用してみると良いでしょう。
無料体験・無料受講相談の申し込みをするほどではないと感じる人は、浅野講師によるガイダンス動画にも情報がありますのでご参考にどうぞ。