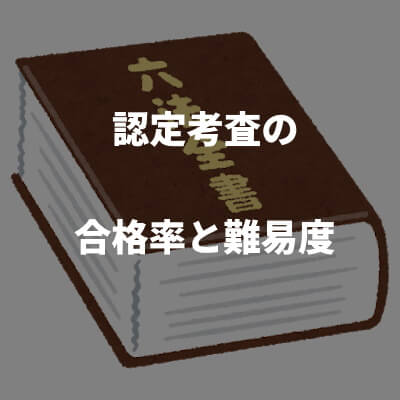おつかれさまです!資格ワン運営の司法書士「よしと」です。

司法書士の認定考査の合格率はどのくらい?
予備校の対策講座は受けたほうが良い?
テキストは何がおすすめ?過去問はある?
そんな疑問はないでしょうか?
この記事では、
|
について説明していきます。
司法書士試験に合格後、すぐに行われた簡裁訴訟代理等能力認定考査で無事認定を受けた私が司法書士の認定考査について解説していきます。
認定考査の合格率の推移
簡裁訴訟代理等能力認定考査の合格率はどのくらいあるのか?
認定考査の合格率(=認定率)は法務省の簡裁訴訟代理等能力認定考査のページに掲載されています。
| 受験者数 | 認定者数 | 合格率 | |
| 令和4年度(2022年) | 643人 | 420人 | 65.3% |
| 令和3年度(2021年) | 591人 | 417人 | 70.6% |
| 令和2年度(2020年) | 625人 | 494人 | 79.0% |
| 平成31年度(2019年) | 936人 | 746人 | 79.7% |
| 平成30年度(2018年) | 874人 | 377人 | 43.1% |
| 平成29年度(2017年) | 915人 | 526人 | 57.5% |
| 平成28年度(2016年) | 940人 | 556人 | 59.1% |
| 平成27年度(2015年) | 987人 | 649人 | 65.8% |
| 平成26年度(2014年) | 1,062人 | 741人 | 69.8% |
となっており、40%代から80%近くまで認定考査の合格率は乱高下しています。
しかし、認定考査は合格率が低いときでも司法書士試験の合格率と比べるとかなり高いです。
認定考査の合格率が大きく変化する理由
認定考査の合格率がこんなにも乱高下する理由は、認定考査は司法書士試験とは違い絶対評価で合格が決まるからです。
認定考査は「70点満点中40点以上」で合格できます。
このことは法務省の資料に明記されています。
毎年40点以上という固定された基準点が示されています。
理論上、認定考査の難易度によって基準点を上下させることが可能ですが、実際には毎年40点以上とされているため合格率が乱高下します。
これが相対評価である司法書士試験の合格率の推移と大きく違う理由。
では、実際に認定考査の難易度はどのくらいなのか?
学生のころから馴染みのある偏差値を計算してみました。
認定考査の難易度を偏差値からみる
認定考査の合格率は乱高下していますが、実際に認定考査はどのくらい難しいのか?
合格者の偏差値を計算してみた結果が以下のとおり。
| 合格率 | 合格基準点の偏差値 | |
|
一番合格率が高い認定考査 (平成31年度) |
79.7% | 約44.01 |
|
一番合格率が低い認定考査 (平成30年度) |
43.1% | 約53.09 |
合格率で比べるとかなり難易度が高い年があるように感じますが、それでも合格者の最低偏差値は53.09です。
偏差値でみると司法書士試験合格者にとっては、認定考査はそこまで難しい試験ではないことがわかります。
スポンサーリンク
認定考査はすぐに受けるのがおすすめ
司法書士試験の合格後は合格証授与式や名刺印刷、事務所探し、新人研修など忙しくなります。
簡裁訴訟代理権を取得するために5月~7月にかけて特別研修を受けて無事修了すると9月第2日曜日にある簡裁訴訟代理等能力認定考査を受験することができます。
晴れて認定考査に合格すれば簡裁訴訟代理権ゲットです。

認定考査はいつでも受けられるから今年は受けない
という合格者もたまにいますが絶対にすぐに受けるべきです。
その理由は以下の4つ。
| 認定考査をすぐ受ける理由① | 司法書士試験合格後すぐに受けるなら簡単な試験 |
| 認定考査をすぐ受ける理由② | 翌年以降に特別研修を受けるとアウェー |
| 認定考査をすぐ受ける理由③ | 後にするほど特別研修の時間確保が難しくなる |
| 認定考査をすぐ受ける理由④ | 「裁判をやる気はないから」では仕事は逃げる |
この4つの理由についてもう少し詳しく解説していきます。
理由1:すぐ受けるなら簡単な試験
認定考査は司法書士試験に比べるとそんなに難しい試験ではありません。
平成31年度の合格率79.7%とかなり高く、近年で一番低かった平成30年度でも合格率43.1%です。

合格率43.1%あるなら、普通に勉強すれば合格しそう
難関の司法書士試験に合格した方であればそう思えるのではないでしょうか?
認定考査の受験者は新人だけではなく、以前の認定考査に合格していない方も含まれています。
つまり、認定考査を毎年受け続けている方もいるということです。
新人に限定するのであれば、合格率は全体よりたぶん上。
なぜなら、司法書士として仕事をしているとごく一部の事務所を除いて民事訴訟法に触れる機会はほとんど無くなるから。
合格から時間が経てば経つほど民訴の知識を忘れ、認定考査の合格が難しくなっていくのです。
今年の司法書士試験に合格した人にとって認定考査は難しい試験じゃないです。
司法書士試験のときと同じように勉強すれば余裕で合格できるでしょう。
理由2:次回以降に特別研修を受けるとアウェー
5月から始まる特別研修に参加すると一緒に新人研修を受けていたメンバーとまた一緒になります。
だから、翌年以降の特別研修に参加する場合、初めまして!な人たちとグループを組んで発表などをすることになります。
しかも、他のメンバー同士はお互いに顔見知り。
非常にアウェーな空気の中で研修を進めることになるのでなかなかに大変です。
司法書士白書によると、平成29年度に特別研修を受講した人数は605人。
平成29年度の司法書士試験の合格者が629人ですからおよそ96%の方がすぐに特別研修を受講しています。
後で特別研修を受ける場合、コミュニケーション能力がすごく高い人であれば「新人研修と合わせて2年分の知り合いができて超ラッキー!」とポジティブに捉えることも可能かもしれませんけどね。
理由3:後にするほど特別研修の時間確保が難しい
まだ事務所に勤めていない人は時間があるはずなので、特別研修を受ける時間的余裕があります。
合格後にすでに事務所に勤めている人は、事務所も新人研修・特別研修に喜んで送り出してくれるところがほとんどのはず。
しかし、翌年に特別研修を繰り越してしまうと、仕事に慣れて事務所の戦力となってきた頃に仕事を抜けなくてはならなくなります。
新人ならいざしらず、1年の間に仕事を覚えた人間が事務所にいないのは痛手。
特別研修に参加しながら事務所の仕事もこなすのが標準となるでしょう。
仕事と研修を両立するのはかなり大変です。
だから、新人研修とセットで特別研修も修了しておいた方が良いのです。
理由4:「裁判をやる気ないから」では仕事は逃げる

私は司法書士として訴訟関係はやるつもりないから別に受けなくてもいいや
そんな考え方だとあなたが独立しても仕事を依頼してもらえないかもしれません。
なぜなら、世間でも関心の高い成年後見業務などでも簡裁訴訟代理権を使う機会があるからです。

あの先生に仕事をお願いしても全部の面倒は見てくれない
とお客様に判断されてしまえば、じゃあ全部やってくれる他の先生に頼んだ方がいいやという結果になります。
そりゃそうですよね。
実際に使う使わないはともかく、仕事が来たらできる状態を作っておくのは絶対に必要なんです!
司法書士試験合格者数と認定考査合格者数の比較
実際に司法書士試験合格者の多くが、翌年に行われる簡裁訴訟代理等能力認定考査を受験して合格しています。
ブロックごとの司法書士試験の合格者数と認定考査の合格者数を比較してみましょう。
|
2018年司法書士試験 合格者数 |
2019年認定考査 合格者数 |
|
| 東京 | 293人 | 339人 |
| 大阪 | 124人 | 158人 |
| 名古屋 | 43人 | 58人 |
| 広島 | 44人 | 46人 |
| 福岡 | 56人 | 76人 |
| 仙台 | 28人 | 38人 |
| 札幌 | 21人 | 15人 |
| 高松 | 12人 | 16人 |
認定考査の合格者数は前年の司法書士試験の合格者数とそこまで大きな差はなく、前年の司法書士試験合格者の多くが認定考査に合格していると推測できます。
簡裁訴訟代理等能力認定考査の勉強法
認定考査を受験するためには、前提として特別研修を修了している必要があります。
しかし、ただ特別研修を受けるだけでは認定考査に合格することはできません。
なぜなら、特別研修は試験対策ではなく、実務寄りの内容だからです。
そのため、特別研修とは別に認定考査対策の勉強も必要となります。
認定考査対策の勉強法として以下の3点について解説していきます。
|
認定考査対策講座は不要
司法書士試験に合格したばかりで、特別研修を受けて認定考査に臨む方には対策講座は特に必要ありません。
認定考査はテキストだけで十分合格が可能。
一方、司法書士試験に合格してから数年のブランクがある人には対策講座はおすすめ。
おすすめテキストは「認定司法書士への道」
簡裁訴訟代理等能力認定考査対策のテキストも色々なものが販売されていますが、あれもこれもとテキストを買う必要はありません。
認定考査合格のためには1種類のテキストを読み込めば十分です。
おすすめテキストは伊藤塾の蛭町浩先生が書いている「認定司法書士への道」です。
予備校講師が書いているテキストなだけあり、試験に合格するために必要な知識を分かりやすく解説しています。
特別研修は研修であり、認定考査は試験です。
受験に慣れた人にとっては研修の内容よりも、テキストで勉強して認定考査に合格する方が簡単でしょう。
「認定司法書士への道」は以下の3種類あります。
この3冊をやっておけば認定考査は怖くありません。
認定考査の過去問はお好みで
簡裁訴訟代理等能力認定考査対策は前述のとおりテキストをしっかり勉強すれば合格可能。
しかし、それでも過去問を解いておきたいという方もいるでしょう。
過去問を解き出題形式に慣れておくのは認定考査でも有効。
テキストに加えさらに勉強したい人は、過去問をやっておいても良いです。
認定考査の直近5年分の過去問は法務省の簡裁訴訟代理等能力認定考査のページにて公開されています。
しかし、法務省で手に入るのは問題文だけですので、試験対策をするなら問題文と解説がセットになっている以下のような書籍を購入したほうが良いです。
司法書士の認定考査の合格率・難易度・テキスト・過去問まとめ
近年の認定考査の合格率は43.1%から79.7%と幅広くなっています。
合格率の幅が広いのは認定考査が70点満点中40点という絶対評価で合格が決まるからです。
問題の難易度によって合格率は下がりますが、合格率が低い年でも偏差値にして53くらいあれば合格することができます。
このように認定考査はそこまで難しい試験ではありません。
司法書士試験合格後、認定考査はすぐに受けるほうが有利。
そこまで難しい試験ではありませんが、勉強しなければ確実に不合格になりますので、テキストを中心にしっかりと勉強するのがおすすめ。
司法書士試験に合格してから研修に専念していた人も、認定考査まで終われば一通りの研修と試験は終了です。
今後は司法書士として働いていくのか、それともさらなるステップアップを目指すのか自分に合った選択をしてください。