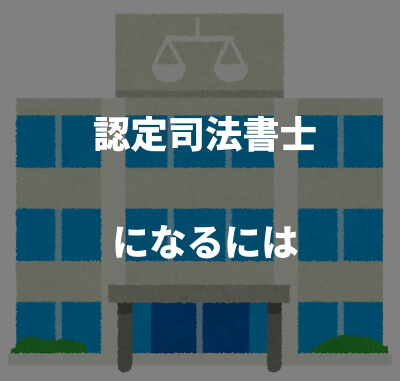おつかれさまです!資格ワン運営の司法書士「よしと」です。

認定司法書士って普通の司法書士とはどう違うの?
将来は裁判業務で困っている人の力になりたいのだけれど、認定司法書士になるにはどうすれば良いの?
そんな疑問はないでしょうか?
この記事では、認定司法書士と普通の司法書士との違い、認定司法書士ができる業務範囲、認定司法書士になるにはどうしたら良いのか、認定司法書士になるまでの流れについて説明します。
司法書士試験に合格後、翌年6月の簡裁訴訟代理等能力認定考査で認定を受けた私が流れについて解説していきます。
認定司法書士とは
認定司法書士とは、通常の司法書士の業務範囲に加えて司法書士法第3条1項6号~8号の訴訟代理等の業務ができる司法書士です。
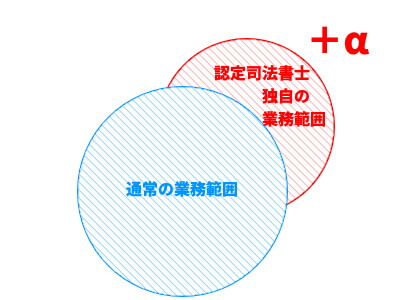
+αされる司法書士法第3条1項6号~8号の内容を簡単にまとめると
|
ということです。
筆界特定手続きの代理は、
固定資産税評価額 × 1/2 × 0.05(法務省令で定める割合)≦ 140万円
という条件から、固定資産税評価額の合計が5,600万円以下と計算することができます。
簡易裁判所の手続きであれば何でもできるわけではないので注意しましょう。
認定司法書士ができる業務できない業務の例
| できる | できない |
|
|
司法書士試験の問題みたいになっていますが、認定司法書士は簡易裁判所に関する業務が何でもできるわけではありません。
|
などは基本的にNGです。
でも、認定司法書士は絶対ダメ!と完全排除してしまうと依頼主に損害が出てしまう危険性があるので、
|
と一部だけ例外として認められています。
スポンサーリンク
司法書士を目指す人は認定も受けた方が良いのか
認定司法書士として裁判関係の仕事をバリバリこなしている司法書士はあまり多くはありません。
しかし、司法書士として仕事をしているとお客様から「~~ということで困っている」という相談を受けることがあります。
その問題を解決するために認定が必要となることがあるため、司法書士に合格したのであれば認定は受けておくべきです。
他の資格を勉強してダブルライセンスを目指すよりも費用が安く、業務にも役立つでしょう。
認定司法書士になるには
認定司法書士になるには以下のような流れが必要になります。
- 司法書士試験に合格する
- 特別研修を修了する
- 簡裁訴訟代理等能力認定考査に合格する
- 司法書士登録をする
認定司法書士になるには1:司法書士試験に合格する
当たり前のことですが、認定司法書士になるにはまず司法書士になる必要があります。
司法書士になるには司法書士試験に合格しなければならず、認定司法書士になるにはここが一番の難関です。
逆に言えば、司法書士試験にさえ合格していれば認定司法書士になるのはそこまで難しいことではないとも言えます。
司法書士の新人研修は働きながら受けられる?合格後の流れ【勤務・独立】
認定司法書士になるには2:特別研修を修了する
例年11月に司法書士試験の最終合格発表があります。
そして合格者は新人研修と特別研修を受けることができます。
新人研修と特別研修は司法書士試験合格後すぐに受けなければならないものではありませんが、合格者のほとんどが合格後すぐに研修を受けるのであなたもすぐに受けた方が良いでしょう。
認定司法書士になるには、この特別研修の修了が必須です。
なぜなら、特別研修の修了証書が簡裁訴訟代理等能力認定考査の受験資格になっているからです。
|
特別研修の概要 |
|
| 開催時期 | 5月~7月 |
| 開催場所 |
以下の8地区で開催されます。関東はさらに細分化されています。
|
| 内容 |
|
| 修了要件 |
|
| 研修費用 | 14万~15万円ほど |
特別研修の修了要件を満たすためには「所定の課程を全て受講」することが必要であるため、以下のいずれかに該当するとその時点で修了できないことが決定します。
|
正当事由のある遅刻は特例の補講措置がありますが、欠席に特例はありません。
途中でインフルエンザ等に罹って研修を受けられなかったらその時点で「また来年」が確定します。
研修費用の約15万円はドブに捨てることになります。
そのため、特別研修を受ける人は遅刻に気をつけるのはもちろん体調管理が一番大事です!
また、新人研修は基本的に座学であり出席していればOKですが、特別研修は課題、質問、発表も多く内容はかなりハード。
課題が多く出されるので、平日に仕事をしていると期間中は特別研修だけでいっぱいいっぱいになります。
認定司法書士になるには3:簡裁訴訟代理等能力認定考査に合格する
7月に特別研修が終わり、無事修了すると8月中旬ごろまでに簡裁訴訟代理等能力認定考査の申し込みを司法書士会にします。
そして、少し間が空いた9月の第2日曜日に認定考査があります。
| 簡裁訴訟代理等能力認定考査の概要 | |
| 開催時期 | 9月第2日曜日 |
| 開催場所 |
|
| 内容 | 事実認定の手法に関する能力、弁論及び尋問技術に関する能力、訴訟代理人としての倫理に関する能力その他簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を習得したかどうかについて、記述式により行う。 |
| 認定要件 | 70点満点中40点以上 |
| 受験料 | 10,900円 |
簡裁訴訟代理等能力認定考査は司法書士試験に比べればずっと簡単な試験です。
きちんと対策をすれば問題なく認定が受けられますので司法書士試験に合格してからしっかりと準備をしてください。
| 関連記事:【司法書士】認定考査の合格率・難易度は?おすすめのテキスト・過去問 |
スポンサーリンク
認定司法書士になるには4:司法書士登録をする
認定司法書士になるには司法書士である必要があります。
さきほどはそのために司法書士試験に合格する必要があると言いました。
しかし、司法書士試験に合格しただけでは司法書士ではありません。
試験合格後に司法書士登録をすることで初めて司法書士となります。
認定司法書士になるには司法書士登録の時期はいつでも構いません。
試験合格後にすぐ登録し、認定考査に合格すれば認定司法書士になれます。
試験合格後に認定考査に合格し、数年後に司法書士登録をしても登録をしたときから認定司法書士になれます。
認定司法書士になるにはまとめ
司法書士が簡易裁判所での訴訟手続等を代理するためには認定司法書士になる必要があります。
認定司法書士になるまでの流れは以下のとおり。
- 司法書士試験に合格する
- 特別研修を修了する
- 簡裁訴訟代理等能力認定考査に合格する
- 司法書士登録をする
このうち、司法書士登録は司法書士試験合格後であればいつでも構いません。
特別研修は約15万円、認定考査は10,900円かかります。
費用が足りない人には司法書士試験合格者を対象とした研修費用専用のローン制度もあります。
まずは司法書士試験に合格することが先決ですが、合格した人は認定考査も受けて認定司法書士として業務ができるようになりましょう!