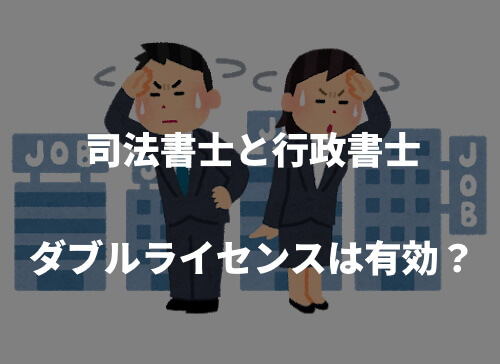おつかれさまです!資格ワン運営の司法書士「よしと」です。

行政書士に合格したら司法書士も受けてダブルライセンスを目指した方が良い?
司法書士と行政書士のダブルライセンスのメリットとデメリットは何?
司法書士合格者が行政書士、行政書士合格者が司法書士を目指すにはどう勉強はどうしたら良いかな?
そんな風に思っていませんか?
この記事では司法書士と行政書士のダブルライセンスについて以下の点について説明します。
|
私自身は4回目の受験で司法書士試験に合格しました。
その後、事務所勤務を経て現在は司法書士として独立開業し、行政書士試験にも合格しましたが行政書士の登録はしていません。
実務家の観点から、司法書士と行政書士のダブルライセンスのメリット・デメリットと必要性、勉強法について解説していきます。
司法書士と行政書士のダブルライセンスは必要?
行政書士とのダブルライセンスは、あなたのやりたい業務がダブルライセンスに向いているかどうかで必要性が違います。
おそらく、予備校はダブルライセンスをおすすめしてくるでしょう。
なぜなら、単純にダブルライセンスを目指してくれた方が予備校の売上が増えるからです。
あなたにとって行政書士資格が本当に必要なのか、メリットとデメリットを見極めてから勉強をするか決めましょう。
ダブルライセンスのメリット
司法書士と行政書士のダブルライセンスのメリットは以下のとおり。
|
ワンストップサービスで報酬増
一人のお客様を相手にしていても、司法書士の独占業務と行政書士の独占業務の両方をこなすことができれば当然報酬も多くもらうことができます。
さらに、司法書士行政書士事務所であれば、他の司法書士や行政書士と連絡を取りながら仕事を進める必要がないため、仕事のスピードアップを図ることも可能です。
お客様が増える可能性
また、司法書士と行政書士それぞれ単独の仕事もすることができるので、片方だけよりもお客様の幅は広がります。
このように、司法書士と行政書士のダブルライセンスになることで仕事の量と報酬を増やせる可能性があるのがメリットと言えるでしょう。
このメリットの説明だけでは予備校の宣伝文句と同じ。
そこで、ダブルライセンスのデメリットについても説明していきます。
ダブルライセンスのデメリット
司法書士と行政書士のダブルライセンスのデメリットは以下のとおり。
|
同業からの紹介案件の減少
例えば、ある行政書士の先生が司法書士の独占業務部分についてだけ、司法書士にお願いしようと思ったとき、
|
・司法書士資格だけの人 ・司法書士+行政書士資格の人 |
がいたら司法書士資格だけの人に仕事を紹介するでしょう。(他の条件はほぼ同じ場合)
なぜなら、司法書士だけの人に紹介した方が、逆のケースがあったときに行政書士の仕事を紹介してもらえる可能性は高いからです。
司法書士+行政書士兼業の人に紹介しても、後の見返りがあまり期待できないからです。
そのため、あなたが司法書士と行政書士のダブルライセンスで仕事をしようと思っているのであれば、お客さんはほぼ自分の力だけで集める必要があります。
営業力に自信がある人でないと厳しくなるかもしれません。
全ての業務に役立つわけではない
司法書士の業務によってはほとんど行政書士資格を使うことが無い場合もあります。
もちろん、その逆も然り。
例えば、相続を中心業務とするのであれば相続登記申請や遺産承継業務などを行うことになりますが、行政書士資格を使うことはあまり多くはありません。
農地の移転登記をするのであれば農地転用許可など行政書士資格が役立つこともありますが、農地以外では使うことはないでしょう。
このように、司法書士や行政書士としてどのような仕事をメインにするかによってダブルライセンスが活用できるかはかなり異なります。
二重に会費がかかる
司法書士登録をすると司法書士会費、行政書士登録をすると行政書士会費を払うことになりるので、二重に会費を支払うことになります。
士業は固定費を抑えて開業できることもメリットなので、司法書士と行政書士のダブルライセンスは固定費の増加というデメリットになります。
また、両方登録したものの片方の業務ばかりであれば、もう片方はほとんど赤字状態となってしまいます。
このように

せっかくだから行政書士or司法書士も受けておこう
くらいの軽い気持ちだとデメリットの方が大きくなる可能性があります。
そのため、あなたのやりたい業務が司法書士と行政書士のダブルライセンスに向いているのかどうかをしっかり見極める必要があるんです。
では、実際にどういう業務をするのであればダブルライセンスが役立つのかを見ていきましょう。
司法書士+行政書士のダブルライセンスが役立つケース
司法書士と行政書士のダブルライセンスは以下のような業務で役立ちます。
|
商業登記では、設立する会社の業務によっては許認可申請が必要となります。
また、既に営業している会社でも追加で許認可申請など行政書士資格が役立つ仕事がもらえることもあるでしょう。
商業登記を主な業務とする場合、司法書士・行政書士のダブルライセンスは有効活用しやすいと言えます。
また、農地法の許可が必要となる農地の移転が多い地方であれば自然と行政書士資格の出番も多くなります。
中には農地を相続したが、相続登記に加えて売却の登記までお願いしたいというお客様もいます。
司法書士試験でも農地はよく出てくる論点ですが、実務でも同様に農地を扱う機会は意外と多いです。
このように、あなたが司法書士・行政書士を兼業してどのような業務をしていくのかを明確にイメージできているのであれば、司法書士と行政書士のダブルライセンスは強力な武器になる可能性があります。
では、司法書士と行政書士の両方取ろうと思ったらどうやって勉強するのが効率的なのかを解説していきます。
司法書士合格からの行政書士勉強法
司法書士と行政書士は以下の科目が重複しています。
| 行政書士試験 | 司法書士試験 |
| 民法(11問) | 民法(20問) |
| 憲法(6問) | 憲法(3問) |
| 商法(5問) | 商法(9問) |
一方で、
|
は行政書士試験でしか出題されないので、対策が必要です。
行政書士試験の勉強法は
|
の2種類が考えられます。
司法書士試験に合格できる実力があれば、独学で行政書士試験に合格することも十分に可能です。
しかし、行政書士試験対策が甘く不合格になってしまう人も毎年結構います。

まぁ独学で受かればラッキー
みたいな姿勢で受けるのであればどうせ資格も活用しないでしょうから始めから受けない方が良いかと思います。

行政書士も生かして仕事がしたい!
と思うのであれば、予備校や通信講座を使って早く行政書士試験に合格してしまった方が良いです。
司法書士試験受験生向けの重複科目を省いた行政法・一般知識中心の講座もあります。
通常の行政書士試験の通信講座に比べて割安なので比較的おすすめです。
行政書士合格後の司法書士勉強法
先程も挙げたように、司法書士と行政書士は以下の科目が重複しています。
| 行政書士試験 | 司法書士試験 |
| 民法(11問) | 民法(20問) |
| 憲法(6問) | 憲法(3問) |
| 商法(5問) | 商法(9問) |
しかし、問われる内容の細かさは異なります。
憲法は行政書士試験の方が難しいくらいですが、民法の細かさ(特に担保物権)と会社法・商法の細かさは司法書士試験の方が圧倒的です。
そのため、あなたに合うと感じられる予備校・通信講座を利用するのがおすすめです。
独学で合格を目指すのは難しく、基本的にはおすすめしませんが、行政書士試験で自分の勉強スタイルを確立できていれば可能な場合もあります。
司法書士と行政書士のダブルライセンスまとめ
司法書士と行政書士のダブルライセンスは、
|
といったメリットがありますが、
|
といったデメリットも考えられます。
そのため、あなたがやりたいと考えている業務で司法書士・行政書士資格の両方を使う機会が多いかどうかがダブルライセンスを取るかの目安になります。
特に商業登記や、農地を扱う可能性が高い場合には行政書士とのダブルライセンスが有効に機能しやすいでしょう。
毎年多くの司法書士試験合格者が行政書士も受験しますが、不合格になる人も結構多いです。
独学で合格を目指すことも十分に可能ですが、行政書士資格を使う予定があるのであれば司法書士合格後すぐに予備校を利用してすぐに行政書士試験にも合格してしまった方が勉強に無駄がありません。
行政書士合格後に司法書士試験に進む場合も、基本的には予備校・通信講座を使うのがおすすめです。
司法書士と行政書士のダブルライセンスは必須ではありません。
片方の資格だけでも十分に仕事をすることができます。
しかし、あなたが行う業務によってはダブルライセンスが強力な武器となることもあるでしょう。
あなたがどんな士業になりたいのか、それに合わせて他方を受けるのか受けないのかを決めてくださいね。