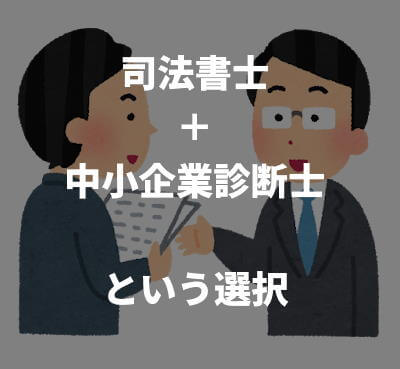おつかれさまです!資格ワン運営の司法書士「よしと」です。

司法書士と中小企業診断士の兼業ってアリなの?
司法書士のあとに中小企業診断士を取るメリットとデメリットは何?
中小企業診断士試験って難しいかな?
司法書士合格者はどうやって勉強するのが良い?
そんな風に思っていませんか?
この記事では司法書士合格後の中小企業診断士試験について以下の内容を説明します。
|
私自身は4年かけて司法書士試験に合格し、現在は独立開業しています。
司法書士合格後に中小企業診断士も検討しましたが、結局勉強はしていません。
司法書士実務の観点から、司法書士と中小企業診断士の兼業のメリット・デメリットなどについて説明していきます。
司法書士と中小企業診断士の兼業はアリ
司法書士と中小企業診断士の兼業は人によっては大いにアリです。
司法書士だけでも独立して業務はできます。
中小企業診断士に合格している場合は、そこに中小企業診断士のブランド力を足すことができるので、司法書士でも商業登記や会社法務を主軸にしたい人には効果が高いです。
司法書士のダブルライセンスと言えばまず行政書士で、司法書士を足がかりに司法試験予備試験の勉強を始める人も多くいます。
しかし、司法書士から中小企業診断士を組み合わせる人はあまり多くないので司法書士と独立してからも他事務所と差別化ができます。
ただし、商業登記・会社法務特化事務所にする場合でも中小企業診断士は必須資格ではありません。
メリットとデメリットをよく把握してから中小企業診断士を目指すかどうか決めましょう。
司法書士の後に中小企業診断士を受けるメリット
司法書士に合格した後に中小企業診断士を受けるメリットをまとめると以下のとおり。
|
司法書士+中小企業診断士のメリット |
|
それぞれのメリットについて少し詳しく説明していきます。
商業登記・会社法務特化をアピールできる
司法書士は会社法が試験科目であり商業登記や会社法務に役立ちます。
そのため、中小企業の経営方針を実現するためにどのようにすれば良いのかをサポートすることができます。
一方、中小企業診断士は中小企業の問題点を解決する相談を受けたり、経営方針を決めるためのサポートをすることができます。
このように、中小企業を相手として、司法書士と中小企業診断士の業務は分野は違えどもつながっている業務です。

登記申請・会社法務もおまかせください!
よりも

登記申請・会社法務から経営相談まで全ておまかせください!
と言えた方が専門性の高さをアピールできますよね。
実際に司法書士+中小企業診断士で「商業・法人登記」「企業法務」「経営・法務コンサルティング」に特化している事務所もあります。
中小企業診断士の名前で独立できる
中小企業診断士の資格を取ると、中小企業診断士事務所を開業することができます。
しかし、中小企業診断士の資格だけではなかなか厳しく、中小企業診断士事務所として独立している人はほとんどいません。
しかし、司法書士はそれだけでも十分独立できる資格ですので、司法書士・中小企業診断士事務所と合わせることで中小企業診断士として独立がしやすくなります。
また、「司法書士・中小企業診断士事務所」と名乗れば誰の目から見ても得意分野が分かるのでお客さんへのアピール度も高まります。
中小企業診断士は名称独占資格なので、資格を持っていなければ「中小企業診断士」を名乗ることはできません。
集客がしやすい

司法書士ってどんな仕事をしているの?
行政書士みたいなものでしょう?
一般的に多くの人がこのような印象を持っています。
しかし、中小企業診断士が事務所名についていれば、事務所の特色が誰の目から見ても分かりやすくなるので、ターゲット層を集客しやすくなります。
ネット検索でも、

企業のコンサルティングが得意な司法書士です
よりも

企業のコンサルティングが得意な司法書士・中小企業診断士です。
の方が説得力があり集客しやすいのは明らか。
また、司法書士は独立開業すると「地域の商工会や商工会議所」に入ることができます。
商工会などはその地域の中小企業や個人事業主が集まっていますが、商工会などでは企業経営に関するコンサルの案内が非常に多いです。
司法書士として所属した場合でも登記申請に関して相談を求められることがありますが、中小企業診断士もあれば経営相談もできるため、商工会などで大量にお客さんが増やしやすいと考えられます。
司法書士+中小企業診断士であれば、商工会などにお客さん候補がたくさんいることが明らかなのです。
司法書士だけでなく中小企業診断士も取れば、自分で一から営業をするよりは効率的にお客さんを増やしていけると言えるでしょう。
ブルーオーシャン
司法書士のダブルライセンスの定番と言えばまず行政書士です。
実際、「司法書士・行政書士事務所」として開業している人も多くいます。
しかし、司法書士と中小企業診断士とのダブルライセンスにする人は少ないため、競争相手が少ないと言えます。
司法書士業務だけで考えてみても、不動産登記や相続を中心に扱う事務所が多く、東京などの大都市を除けば商業登記特化の事務所は数が少ないです。
その中で中小企業診断士の資格もあれば地域のオンリーワンを目指すこともできるでしょう。
司法書士と中小企業診断士のダブルライセンスは、司法書士業務の中では他との競争があまりないブルーオーシャンと言うことができます。
| 関連記事:「司法書士合格→行政書士のダブルライセンス解説【実務家視点】」 |
スポンサーリンク
司法書士の後に中小企業診断士を受けるデメリット
司法書士に合格した後に中小企業診断士を受けるデメリットをまとめると以下のとおり。
|
司法書士+中小企業診断士のデメリット |
|
デメリットについて詳しく解説していきます。
難易度が高い
中小企業診断士試験は1次試験、2次試験の合格率がそれぞれ20%前後の難易度が高い試験です。
単純な合格率だけで言えば司法書士の合格率5%よりも高く、難易度的には司法書士の方が少し難しいです。
しかし、中小企業診断士の試験科目は司法書士とあまり関連がないため、司法書士に合格していることによる勉強面でのメリットはあまりありません。
一般的には中小企業診断士に合格するまでに必要な勉強期間は平均3年間と言われています。
しかし、必要な勉強時間は1000~1500時間くらいと言われているため、司法書士と同様に勉強できれば1年での合格も不可能ではないでしょう。
じっくり勉強して中小企業診断士を目指すのであれば良いのですが、働きながら中小企業診断士の勉強もするとなると結構大変。
司法書士に受かったから、とついで感覚で勉強を始めるにはきつい試験だと言えるでしょう。
商業登記・会社法務以外のシナジーが弱い
司法書士として商業登記・会社法務に特化していくつもりでなければ、中小企業診断士に合格してもほとんど役に立ちません。

司法書士として独立したものの、結局不動産登記が中心になってしまった
なんてことになると中小企業診断士に合格しても無駄になってしまうでしょう。
名称独占資格でしかない
中小企業診断士は名称独占資格ですので試験合格者しか中小企業診断士を名乗ることはできません。
しかし、司法書士と違い、中小企業診断士の業務は資格が無くてもすることができます。
中小企業診断士は名称独占資格であっても業務独占資格ではないんです。
コンサル業は資格がなくても誰でもできます。
そのため、司法書士でもコンサルの実績をアピールできれば資格は必要ありません。
お客さんがどう思うかが重要なので、資格でアピールするのか、実績でアピールするのか、あなたの考え方次第では試験勉強をするよりも実務に励む方が有効である可能性があります。
中小企業診断士試験の概要
中小企業診断士の合格に必要な勉強時間はおよそ1,000時間~1,500時間と言われています。
中小企業診断士試験の1次試験の概要をまとめると以下のとおり。
|
中小企業診断士1次試験の概要 |
||||
| 試験日程 | 試験科目 | 試験時間 | 方式 | |
| 1日目 | 午前 | 経済学・経済政策 | 60分 |
4肢択一マークシート (一部5肢択一) |
| 午前 | 財務・会計 | 60分 | ||
| 午後 | 企業経営理論 | 90分 | ||
| 午後 | 運営管理 | 90分 | ||
| 2日目 | 午前 | 経営法務 | 60分 | |
| 午前 | 経営情報システム | 60分 | ||
| 午後 | 中小企業経営・政策 | 90分 | ||
|
各科目100点満点で、全体の60%以上正解すれば1次試験合格。 ただし、40点未満の科目があると1次試験不合格になる。 3年間の科目合格制度あり。 |
||||
中小企業診断士の1次試験は2日間に渡って行われ、科目毎の試験となります。
司法書士試験の基準点と同じく、各科目40点未満になった時点で不合格です。
しかし、科目合格制度があるため、数年かけて合格するのはそこまで難しくないでしょう。
2日目午前の「経営法務」は会社法と民法が含まれているため、司法書士試験合格者にとっては有利な科目です。
しかし、知的財産権に関する法律や金商法なども含まれているので勉強は必要です。
1日目午前の「経済学・経済政策」「財務・会計」は公務員試験でも問われる科目なので、公務員試験経験者は少し有利になるでしょう。
続いて、中小企業診断士試験の2次試験の概要をまとめると以下のとおり。
|
中小企業診断士2次試験の概要 |
||
|
筆記試験 |
||
| 出題 | 試験時間 | 形式 |
| 事例問題4問 | 事例1つにつき80分 | 事例問題1問につき、小問5~10問程度の記述式 |
|
各事例問題100点満点で、全体の60%以上正解すれば筆記試験合格。 ただし、40点未満の科目があると筆記試験不合格になる。 |
||
|
口述試験 |
||
|
筆記試験合格者が後日受ける面接形式の試験。 司法書士試験の口述試験同様、ほぼ受かる試験。 |
||
2次試験のメインは記述式試験です。
択一式と違い科目合格制度はないため、一発で4つの事例問題全てで40点以上を取り、合計が60%以上であれば筆記試験合格です。
筆記試験に合格すれば口述試験はほぼ合格です。
中小企業診断士試験は2次試験の方が少し合格率が低めになっています。
中小企業診断士の勉強方法
中小企業診断士も難易度が高い試験なので予備校や通信講座を使って早めに合格を目指すのが良いです。
予備校や通信講座のおすすめ順は以下のとおり。
|
おすすめ 順位 |
予備校・通信講座名 | 講座・費用 |
| 備考 | ||
| 1 | スタディング |
48,400円~(税込) |
|
司法書士でも有名なスタディングは中小企業診断士から始まった通信講座であるため、中小企業診断士は最も得意とする試験。スマホで隙間時間に勉強しやすいのが強み。 (表示価格は1次2次ミニマムコース。スタンダードコースは53,900円税込) |
||
| 2 |
アガルートアカデミー |
総合カリキュラム 69,800円(税込) |
|
1次・2次試験対策の両方ができることはもちろん、2次試験過去問解析講座(5年分)つき。合格時に全額返金+お祝い金3万円の制度も。 |
||
| 3 | フォーサイト |
108,400円(税込) |
| 比較的安価で1次・2次試験対策ができる。1次試験対策のみの75,600円(税込)のバリューセット1のほか、科目別に申し込むことも可能。 | ||
| 4 | LEC | 1次2次プレミアム合格コース等 22万円~27万円ほど |
|
経済学や財務・会計などをしっかり勉強したい人には大手がおすすめ。LECの中小企業診断士講座は大手の中では安い方。 |
||
| 5 | TAC |
30万円ほど |
|
経済学や財務・会計などをしっかり勉強したい人には大手がおすすめ。司法書士試験でWセミナーを利用していた人など、TACの方が馴染みやすい人におすすめ。 |
||
中小企業診断士に強く、比較的費用も安い講座が3つもあるので基本的にはその3つから選ぶのがおすすめ。
最終的には司法書士同様、無料講義を体験したり、資料をよく読んで内容を検討してから決めましょう。
司法書士と中小企業診断士の兼業まとめ
司法書士と中小企業診断士の兼業は、商業登記や会社法務に特化した事務所にするつもりであれば大いにアリです。
司法書士と中小企業診断士の兼業のメリットは以下のとおり。
| 司法書士+中小企業診断士のメリット |
|
一方、デメリットは以下のとおり。
| 司法書士+中小企業診断士のデメリット |
|
あなたの今後の方針に合わせて中小企業診断士を受けるかどうか決めましょう。
なぜ私自身は中小企業診断士の勉強をしていないのに、中小企業診断士を薦めるような記事を書くのか?
その理由はとても簡単です。
私は司法書士試験では「会社法」「商業登記法」、公務員試験では「経済学」「会計学」が苦手だったのでそこを主力業務にしていこうというつもりが無いからです。
それらが好きで業務としていきたい人にとっては良い選択肢になると思いますよ。
中小企業診断士の試験科目は、司法書士試験の試験科目とあまり重なりがありません。
そのため、しっかりと予備校や通信講座を使って勉強するのがおすすめです。
中小企業診断士試験への専門性が高く、費用も控えめな通信講座があるので、それらを利用すると良いでしょう。
もちろん、価格だけではなく無料体験や資料請求をしてしっかり比較することが大事ですよ。
|
関連記事:「司法書士合格→行政書士のダブルライセンス解説【実務家視点】」 |